AI時代の成長戦略 カタリストCEO出澤が描く、未来からの逆算とは?

組織のカオスを整え、社員の力を最大化する「カタリスト(触媒)」としてのリーダーシップ。
生成AIの進化とともに社会が大きく変わろうとするなか、LINEヤフーとなってから3年目を迎えるCEO 出澤は、自身の役割を「カタリスト」だと表現しました。
産業革命に匹敵する社会変革が起こりつつある今この局面で、CEOとして、どんなことを意識しながら拡大する組織を率いているのか。変化を受け入れて、人と組織の力を引き出す思考と行動の原点に迫りました。

- 出澤剛(いでざわ たけし)
- LINEヤフー 代表取締役社長 CEO(最高経営責任者)
早稲田大学卒業後、生命保険会社に入社。営業担当を経て、2002年にオン・ザ・エッジへ。2007年4月にライブドアの代表取締役社長に就任し経営再建に取り組み、1年半後に通期での黒字化を達成。
買収・経営統合の後、2012年1月にNHN Japanの取締役に就任。2014年1月にLINE(NHN Japanの商号変更)取締役、2015年4月に代表取締役社長CEO、2021年3月からZホールディングス代表取締役Co-CEOを経て、2023年10月にLINEヤフー代表取締役社長 CEO(最高経営責任者)に就任。
困難に立ち向かう戦国武将に憧れた少年期
――今回は、出澤さんの人柄を深掘りしたいと思っていますが、ご自身の性格を一言で表す言葉はあるでしょうか?
あえて、欠点をさらけ出すと、「鈍くさい」ところはあるかもしれませんね。反射神経が少し鈍いというか、嫌なことを言われても翌日になってやっと気づくこともあります。
ライブドア時代には、経営層の逮捕など企業として非常に厳しい局面を経験しました。経営のトップを任された私としては、ユーザーのため、社員のために最後までやりきろうと、真摯(しんし)に向き合い続けたつもりです。後に辞めた同僚から「おまえ、逃げ遅れたな」なんて半分冗談で言われたこともありましたが、あの状況で踏ん張っていた私の姿勢を見てねぎらいの言葉をかけてくれたのだと感じています。
――それは、裏を返せば責任感が強いと言えるのではないでしょうか?
そうかもしれません。頼まれると「嫌だ」とは言いにくい性格ですし、何かを途中で放り出すのは少し格好悪いと感じる。そのとき、そのとき、与えられたポジションで、自分が発揮できる役割を意識しています。
目の前の困難な状況に立ち向かっているうちに環境がどんどん変化していき、今に至っているという感覚です。
――結果的に、任される組織がどんどん大きくなっていたという感覚でしょうか?
そうですね。一見すると目立たない領域を任されて身を置き、真摯に取り組んでいるうちに、やがてそこがメインストリームになり、担当する事業領域やサービスが大きくなっていたという状況はそれ以前にもありました。
たとえば、ライブドア時代、当初メイン領域だったポータル事業ではなく、スタートしたばかりのモバイルコンテンツ事業を任され、やがて、そこがマーケットの成長とともにどんどん大きくなっていったのです。
ですから、変化やイノベーションは周辺から生まれるという感覚が自分のなかにありますね。
――子どもの頃からリーダーを任されることも多かったのでしょうか?
自分から立候補するタイプではなく、中学や高校の部活(ソフトテニス部)などでは周囲からリーダーに推されてやることが多かったですね。
その頃から、「こいつなら責任ある役割を任せても、最後までやってくれるだろう」と思われていたのかもしれません。
――子どもの頃から歴史が好きだったとうかがいました。影響を受けた人物、生き方などはありますか?
司馬遼太郎さんの歴史小説で戦国武将たちの生きざまにひかれました。立派な武将は危機的状況でも諦めずに、局面を打開するんです。そこでの人間模様が面白く、迫力のある物語に引き込まれたものです。
『信長の野望』という歴史シミュレーションゲームにもどっぷりハマりましたが、特に好きだったのは「内政フェーズ」で、農業や商業、工業を整えて、民の生活をよりよくしていく工程です。混沌(こんとん)としたカオスの状態を整えて、次につながる基盤をつくるのが楽しかった。これは今の仕事とも通じるところがありますね。

プロダクト志向への覚醒と視座の転換
――これまでのキャリアで、転機となった出来事はいつ頃でしょうか?
ライブドアで社長になったときですね。それまでは中間管理職として限られた領域の目標に取り組むことが多かったのですが、いきなり全体を見る立場になって、さまざまなステークホルダーの間に立たざるを得なくなったのです。
そこから「未来から逆算して考える」視点を持つようになりました。視野も大きく広がり、同世代の幹部社員と切磋琢磨(せっさたくま)しながら、次のフェーズに引き上げてもらったり、次の階段を一緒に登ったり、視界は大きく開けましたね。
――その後、M&Aでさまざまな経営者との出会いがあったと思いますが、影響を受けた部分、思考の変化などもありましたか?
間違いなく、ありました。10年以上の付き合いになる慎(現LINEヤフーCPO)やイ・ヘジン会長(NAVER創業者で現Aホールディングス会長)との仕事を通じて、「プロダクトファースト」の考え方に触れました。
それまでの日本のインターネット企業ではビジネスドリブンな傾向が強かったと思いますが、インターネット産業にいる以上、「イノベーションを起こしてこそ価値があるし、世の中を便利にすることにこそ意義がある」と、真剣に考える姿勢を学びました。
本当に社会に求められる良いサービスをつくるには、経営レベルで「一球入魂」して取り組み、それを何度も何度も繰り返しチャレンジして、それでも当たるか外れるかわからない。そんな厳しい世界であることを実感しました。慎など、当時のメンバーが、LINEを生み出した時がまさにそうでしたね。
一方で、ヤフーとの経営統合で出会ったソフトバンクグループの孫会長からは、確固たるビジョン、それを実現するための行動力、エネルギーに圧倒されました。あれほどまでに、未来から逆算して動く経営者はいないでしょう。自分の中の物差しが明らかに変わった出会いであり、貴重な経験です。
――これまでのキャリアを振り返って、最も困難だったと思える時期はいつでしょうか?
やはり2021年3月の経営統合直後のタイミングで発生した個人データ管理不備の問題への対応ですね。
ユーザーの皆さまをはじめ、本当に多くの方々にご迷惑、ご心配をおかけしましたし、経営統合でこれから成長を加速させるぞというタイミングで、相当の人的リソースも割かざるを得なかった。経営者として事前に対応できなかったことに忸怩(じくじ)たる思いでしたし、心身ともに一番追い込まれた状況でした。
ただ、サービスに対する誇りがありましたし、使い続けてくださっているユーザーの皆さまの期待に応えたい、信頼を回復しなければならないという思いで、社員にも支えられ、なんとか立ち向かうことができました。

「カタリストCEO」としての役割と覚悟
――LINEヤフーとなって3年目を迎えた今、ご自身はどんなCEOだと自覚されていますか?
変化を促し、組織やメンバー間の連携を促進させるという観点で言うと、「カタリスト」が当てはまるでしょうか。見ての通り、強引に「俺についてこい」とやるタイプではありません。むしろ仲間の強みや適性を見極めて声に耳を傾け、適切なアサインをして化学反応を生み出したり、環境を整えたり、組織力を高めるために行動するタイプです。
LINEヤフーには、学生時代からスタートアップを志向したアントレプレナータイプに加え、M&Aやグローバル化で組織が拡大した経緯もあって、さまざまなタイプの幹部がいます。
私は新卒から大きな組織に入って、今に至っているわけですが、その分、仲間の力や可能性を引き出して、うまくつなぎ、融合させていく、そういうカタリスト(触媒)のような経験が長かったのです。
今のような、価値観も文化も違う大きな組織同士が一緒になったカオスな状態では、そういう役割が求められていると感じることもあります。信頼できる優秀なメンバーが多数いますから、彼らの能力を引き出し、組織力を最大化していくことが、私がCEOとして果たすべき役割だと信じています。
――社員の声に耳を傾けてくれる印象が強いですが、フルリモートワークから出社併用方針への変更など、社内から一定の厳しい声が上がる決断もありました。
これは、多くの社員の生活、人生に影響することなので当然ながら悩みました。
ですが、未来から逆算して、今が組織に大きな変化を起こすべきタイミングだと判断しました。
特に生成AIの急速な進化により、既存のやり方、スピードでは間に合わなくなってきています。既存事業の延長だけならこれまでの働き方でよかったのかもしれませんが、対面での偶発的な議論や創発が、このフェーズには絶対的に必要だと考えました。
どうしても、さまざまな局面でトレードオフの決断を迫られますが、私には会社を持続的に成長させていく使命があります。社員にとってどんなに働きやすい環境でも、会社の成長が止まり、立ち行かなくなれば元も子もありません。
――経営者としてはサービス撤退など、つらい決断もあるかと思います。どんな軸で判断していますか?
ユーザーへの提供価値と、将来性、収益性などをバランスよく見るようにしています。
もちろん、撤退には痛みがあります。ですが、特にインターネット業界の場合はチャレンジと撤退がセットです。今後、AIが進化してビジネスの構造変化が進むなかで、これまで以上にそういった判断が必要になってくるかもしれません。
痛みを伴ったとしても、未来志向で潔く判断することが経営者としての基本動作だと思っています。

生成AI時代に生き残るのは「変化できる組織」
――生成AI時代において、会社としての生存戦略について教えてください。
AI時代の新しいサービスと組織を爆速でつくる、この2つに尽きます。「あらゆる仕事がAIに代替されるのでは?」と言われるほど、非常に大きな社会変革の波がきていますが、この状況は続くでしょう。ですから、変化に適応し続けられるDNA、マインドを作りあげていかなければなりません。
われわれが展開している事業も、生成AIによって大きく変わっていくはず。だからこそ、危機感を持って、スピードと効率を両立しながら、新しい形のプロダクトや組織モデルに日々、アップデートしていかないといけません。
AIエージェントは次々に実装が始まっています。また、先日、全社員のAI活用の義務化を発表しましたが、徹底活用によって生産性を向上させ、その分で、新たなサービスや価値をどんどん生み出していく。とにかくスピード感、切迫感を持って進めていく必要があります。
――AIが進化するなかで、LINEヤフーはどんな強みをどう生かして進化していくべきでしょうか?
劇的にビジネス環境が変わろうとも、われわれが提供していく価値は、変わらずに「ユーザーの毎日に寄り添い、驚きや感動、『WOW』や『!』を届けていくこと」でありたいですね。
よりパーソナライズされたAIの提供は他のグローバルプレーヤーなども類似の構想を描いています。ですが、私たちはすでに日常生活をカバーするサービス群を持っていて、日本国内のユーザーニーズをより深く理解した上で、ユーザーの生活に寄り添うテクノロジーを実装できる地の利があります。台湾、タイなどでも同様ですね。
私たちの目指すAIエージェントの姿も、ユーザー一人ひとりに最適化された体験を届けること。その世界観に、一刻も早く到達できるかどうかが勝負ですね。
――最後に、意気込みとともに、LINEヤフーがどんな存在でありたいかを教えてください。
この激動の時代、「変わり続けられる組織」であることが重要であり、変化を楽しむ私たちはそれを実現できることが強みだと信じています。
この先、評価軸もルールも次々に変わる時代がくるでしょう。その中でも、変化を受け入れ、仲間と力を合わせて新しい社会をつくっていく。
そして、業界はもちろん、日本、アジアをリードしていく。そんなLINEヤフーでありたいし、自分もその変化の起点として、カタリスト(触媒)であり続けたいと思います。

関連リンク
-
リーダーズ

「フェアプレーで未来を創る」 CEO出澤と会長川邊が語るAI時代のコンプライアンス
-
リーダーズ

「真心はいつか必ず通じる」AI戦略を担うCPO慎がいま大切にしたいこと
-
リーダーズ
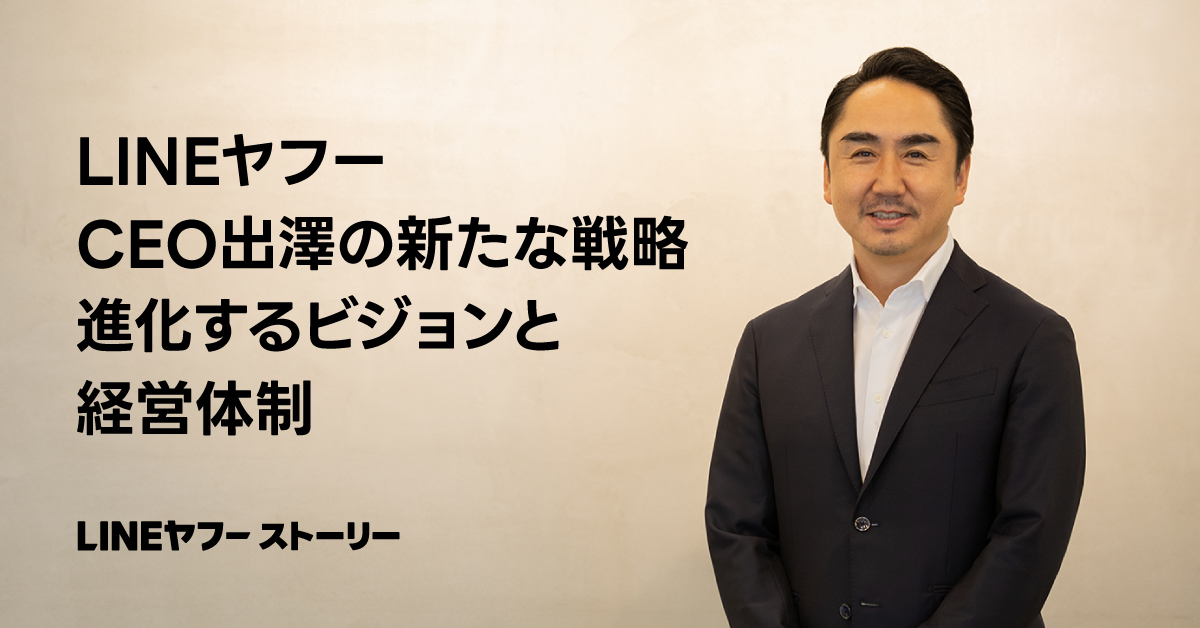
LINEヤフーCEO出澤の新たな戦略 進化するビジョンと経営体制
取材日:2025年7月11日
文:LINEヤフーストーリー編集部 撮影:猪又 直之
※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて
- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。
コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。


