社内弁護士が実現するユーザーファーストとソーシャルインパクトの両立
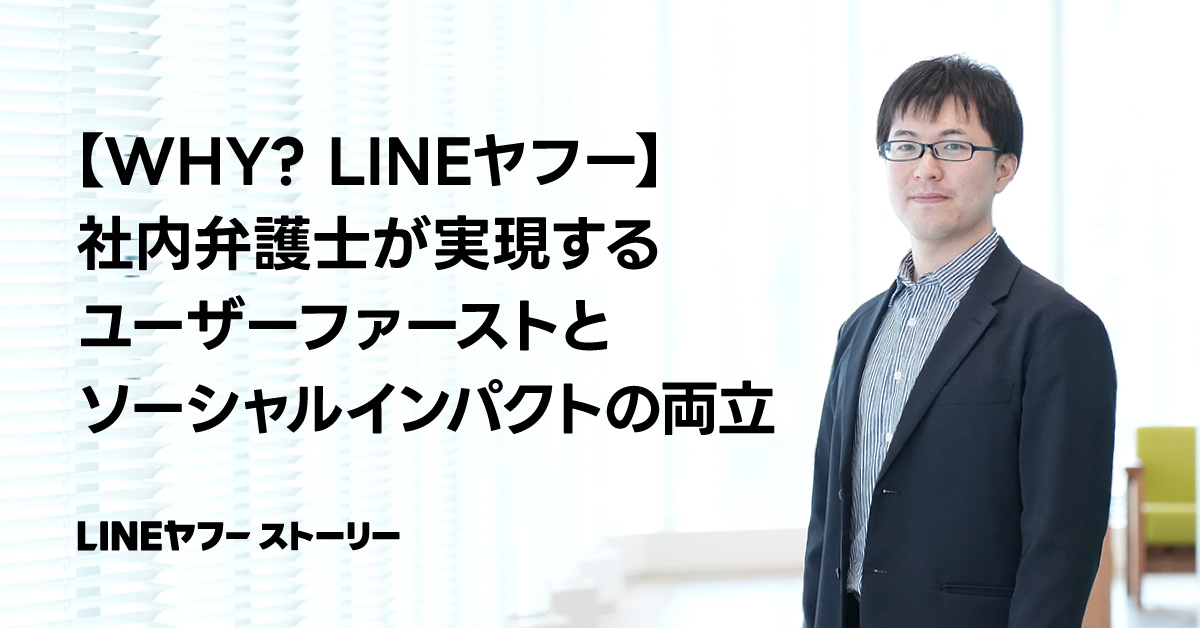
LINEヤフーでは、さまざまな社員が働いています。「WHY? LINEヤフー」シリーズでは、社員の仕事内容や思いを通じて、LINEヤフーで働く魅力をお伝えしていきます。今回登場するのは、"社内弁護士"として働く圓井(つむらい)です。
テクノロジーの進化とデータの活用が進む中、コンプライアンスやプライバシーに対する関心が高まっています。それに応じて、企業法務の重要性と複雑さは一層増しており、日本でも弁護士資格を持つ社員を採用する企業は増加しています。
LINEヤフーでは70名を超える弁護士資格保有者が在籍していますが、日々どのような業務に携わっているのか。社内に弁護士がいることで、サービス開発体制にどのような効果があるのか。LINEヤフーの目指す「『WOW』なライフプラットフォーム」の実現に法律はどのように寄与するのか。圓井のキャリアからその一端を探りました。

- 圓井 隆正 (つむらい たかまさ)
- ガバナンスグループ法務統括本部第一事業法務本部メディア事業法務部
2022年ヤフー(現LINEヤフー)新卒入社。Yahoo!検索、Yahoo!マップ、Yahoo!知恵袋、Yahoo!ニュース・LINE NEWSなどメディア事業の法務に携わりながら、オープン・ソース・プログラム・オフィス(OSPO※1)、データグループ、PIA(※2)なども担当。
※1:企業内でのオープンソースの活用や貢献を推進・管理する部門
※2:ユーザーのプライバシー保護に配慮しているかを検討する事前評価のプロセス
日本でも有数の社内弁護士がサービス作りを支えるLINEヤフー
――圓井さんが弁護士を目指したきっかけはなんだったのでしょうか。
私の父は、薬剤師でありながらプログラマーも兼業していました。その影響もあり、私も既存の価値観にとらわれず、幅広い分野に関わりたいと考えていました。
また、大学時代の会社法を専攻していたゼミや大学院卒業後に少しプログラミングの業務に関わる機会を得たことで、法律を通じてテクノロジーや医療など幅広い分野に貢献できるのではと考えました。
弁護士として、さまざまな領域をつなぐ"ハブ"のような役割を果たせるのではないかと思ったんです。

――弁護士として独立するのではなく、新卒でLINEヤフーに入社した理由を聞かせてください。
ITベンチャー企業とよく取引している法律事務所や企業法務専門の事務所に入社することも視野に入れていました。ですが、よりテクノロジーに近い現場で働くには、と考えたときに、まず思い浮かんだのが当時のヤフーでした。
そもそも弁護士を社員として雇用している企業も日本では限られていますが、ヤフーは早くから弁護士を雇用している実績もあります。また、事業領域もテクノロジーはもちろん、メディア、金融、ECなどと非常に幅広いことも理由でした。
入社後は、Yahoo!検索、Yahoo!マップなどと担当し、2024年下半期からはYahoo!知恵袋、Yahoo!ニュースも担当しています。もともとヤフーでは複数事業を受け持つ体制になっていましたが、LINEと経営統合してLINE NEWSも担当するようになりました。まさに業務内容としても統合が進んでいる真っただ中ですね。
――具体的にはどういった業務に取り組んでいるのですか。
基本的には、各サービスに対する法的な助言を行ったり、契約書や各種作成書類に対する審査を行ったりしています。最近ではデータ利活用や生成AI、LLM(大規模言語モデル)に関する相談や助言を求められることが多く、法的な観点からガイドラインや改善策を提案しています。
――確かに、生成AIやLLMは今まさにダイナミックに発展していて、法的な観点からも留意すべき点がありそうですね。
そうですね、生成AIにはみなさん注目されていると思うのですが、この新たな領域はまだ裁判例なども少なく、法律としても解釈が固まっていないところがあります。ですから、既存の法律に基づいた考え方をベースに、新たな分野に適用したらどうすべきなのか、どのように取り組むべきなのかをリサーチしながら考えていくことが多いです。
当社の弁護士の中には、経営戦略や事業戦略に携わっている人や、官公庁との渉外を行う公共政策を担当する人などもおり、ビジネス・サービス部門に限らずさまざまな部門と関わっています。
新規事業や新規サービスの中には、行政や業界団体への働きかけや法整備が必要な場合もあるため、私たち弁護士が社内はもちろんのこと、社外に対しても法的な考え方に基づき助言や提案を行っていくことが重要です。
ユーザーの権利を守り、よりわかりやすいプライバシーポリシーを
――これまで携わってきた仕事で、特に印象に残っているものはありますか?
ユーザーの皆さまにとっても身近なプライバシーポリシーの策定に携わったことです。LINEとヤフーの経営統合に伴い、プライバシーポリシーもLINEとヤフー各社にあったものを一つに統合することになりました。
プライバシーポリシーは、ユーザーの皆さまがサービスを利用するにあたって同意いただくもので、個人に関する情報(パーソナルデータ)などの取得・利用・管理方法、その利用目的などの取り扱いを明らかにすることで、安心してより良いサービスを利用していただけるようにするものです。
――プライバシーポリシーを統合するにあたってどのような点が難しかったのでしょうか。
個人的には、もともとLINEとヤフーで策定されていたプライバシーポリシーは、それぞれ異なる思想で設計されていたように思います。LINEでは、グローバルで共通して利用することもあり、ユーザーへ詳細に説明することを重視し、具体例を多く記載しているように思いました。一方、ヤフーでは、日本のユーザー向けであり、プライバシーポリシーそのものはできる限り簡潔にまとめ、個別事由についてはプライバシーセンターで対応する形式にしているように思いました。
新しいプライバシーポリシーでは、これら2つのアプローチを踏まえて、具体例を充実させながら、できる限り簡潔にすることを目指しました。
――ユーザーからすれば、わかりやすいのは大前提として、「詳細に説明して透明性を担保してもらいたい」という声もあります。簡潔かつ詳細に、というと一見相反するようですが、どちらも大切ですよね。
その通りです。最終的には、共通する内容をまとめるなどして、私としてはちょうど良いバランスで調整できたのではないかと考えています。また、ポリシーの趣旨をよりご理解いただくためにプライバシーセンターを公開し、イラストや図表、具体事例を交えてわかりやすく説明しています。
――LINEヤフー発足時に、アプリ経由で新しいプライバシーポリシーへの同意が求められました。何か意識した点はありますか?
「ユーザーファースト」を重視する上で、ユーザーにとってのわかりやすさは非常に重要です。そのため、単にプライバシーポリシーで個人情報の利用目的を記載するなどの法的要件を満たすだけでなく、ポップアップでもプライバシーポリシーの要点についてイラストや具体例を表示しています。
法務部門だけでなく、CDO(チーフ・データ・オフィサー)室やDPO(データ・プロテクション・オフィサー)室、広報、開発チームなどさまざまな部門が関与し、デザインやUIなども調整することで、ユーザー自身がデータの取り扱いを理解し、納得して同意していただけるようなプライバシーのあり方を目指しています。

「ユーザーファースト」なサービスの実現を法的にサポート
――LINEヤフーのバリューの一つに「ユーザーファースト」がありますが、社内弁護士にとっても重要な行動指針なんですね。
もちろんです。私たちは、法律を理由に「それは難しい」と消極的な立場を取るのではなく、ユーザー視点を大切にし、サービス部門とともに「どうすれば実現できるか」と模索するよう心がけています。
サービスごとにSlack(コミュニケーションツール)のチャンネルや社内ツールでやりとりを行っていて、企画段階から積極的に意見や助言を求められます。「法的にこういった部分が難しいが、こうすればクリアになる」「サービス価値を社会に提供するためには何が必要か」といった具体的な解決策を提案するよう心がけています。
――「弁護士に相談する」と聞くと少し身構えてしまいそうですが、気軽に相談できる体制が整っているんですね。
そうですね。そもそも、社員一人ひとりがコンプライアンスの意識を持ち「インシデントを未然に防ぐにはどうすればいいか」と、会社全体で考えることができていると思います。
ただ、こうした意識があると、企画やサービスを考える際、逆に法的理由を根拠に「できない」と思い込んで、萎縮してしまうことにもつながりかねません。そのようなときは、弁護士資格を持つ私たちが「この部分をクリアにすれば実現できる」「データをこのように処理すれば、法的に問題ない」と、法的根拠を明示しながら適切に線引きすることが重要です。これにより、企画開発やサービス側の「これを実現したい」を後押しできるからです。
――まさにそれが、社内弁護士の存在意義と言えるかもしれません。
たしかに、社内弁護士だからこそ、各サービスにしっかりと並走しながら、事実関係を逐一確認し、細かく線引きして適切な助言ができます。ユーザーにとって本当に価値あるサービスになるかもしれないのに、法律に関する誤解や心理的な萎縮によって実現できないのは、ビジネスにとっても機会損失になりかねません。
生成AIをはじめ、新しいテクノロジーは急速に進化し状況も刻々と変化しています。最新の状況を踏まえている資料は多くはないため、キャッチアップが難しい部分もありますが、常に既存の法律の枠組みや世間の感覚を考慮する必要があります。専門家によるセミナーや文献を参考にしつつ、SNSやネットを活用して、現在の議論がどうなっているのか、ユーザーの皆さまはどう感じているのかを理解しながら、世間一般の感覚や現場感を持って適切な判断をしていきたいと考えています。

ユーザーファーストの追求とコンプライアンスの遵守は両立する
――LINEヤフーは「『WOW』なライフプラットフォームを創り、日常に『!』を届ける。」というミッションを掲げていますが、その実現のために必要なことはなんでしょうか。
社内弁護士の答えとしては意外に思われるかもしれませんが、やはり「ユーザーファースト」を意識することに尽きると思います。ユーザーファーストを実現するには、「ユーザーの利便性を追求する」だけでなく、「ユーザーに不利益を生じさせない」ことも重要なことです。
ソーシャルインパクトを意識して、多くの人々を驚かせるような優れたサービスやプロダクトを生み出そうとすると、ユーザー視点を見落としてしまいがちです。例えば、既存ユーザーの利便性を重視して説明文をなくすと、本当はクチコミとして公開される情報について新規ユーザーが公開されないと誤解してしまうなど、あるユーザーの利便性を追求するうちに、他のユーザーにとっては意図しない不利益が起こるかもしれません。
そうなれば誤解を解くために追加の対応コストがかかり、ユーザーの信頼を失いかねません。ユーザーにとっての利便性を考えるのと同時に、不利益を生じさせる可能性はないか、サービス側の一方的な視点になっていないかを常に考えるのが大切です。
また、「ユーザー」というと個人を思い浮かべやすいかもしれませんが、LINEヤフーのサービスは多岐に渡り、企業や団体を対象とするものもあります。あらゆるステークホルダーが利便性を享受し、不利益を被ることのないサービスを実現することが、結果的にコンプライアンス遵守につながり、ソーシャルインパクトにもつながると考えています。
――あらゆるステークホルダーと考えると、それぞれ立場や考え方も異なります。すべての人が納得のいく方向性を見つけるのは容易ではありませんよね。
そうですね。だからと言って、誰かの不利益のもとに何らかのサービスが成り立っているとすれば、問題がありますよね。私たち社内弁護士が複数のサービスを担当し、"ハブ"のような役割を担うことで、複眼的な視点から法的な助言や提案ができます。他のプロジェクトで得た知見や経験を別のプロダクトやサービスに活用したり、外部ツールやリソースを提案したりすることもあります。

――圓井さんは今後、社内弁護士としてどのようなことを実現していきたいですか。
まずは、事業やサービスに関わる方々の尽力があるからこそ、法務として活動できるというのをつねに忘れず、しっかりと役割を果たしていきたいです。個人的には、理想論かもしれませんが、将来的にはプロダクトやサービスを開発する際、法律を過度に意識しなくても、法的に問題ない形でリリースできるような環境を整備することを目指しています。
たとえば、オープン・ソース・プログラム・オフィス(OSPO)の活動として、LINEヤフーの経営統合に際し、オープンソースコモンポリシーを策定しました。これは、オープンソースライセンスを遵守するためのルールやガイドラインを策定することで、開発側が適切な手続きを行えるようにすることが目的です。
現在、このポリシーは社内で公開し、個別の相談不要で開発側で対応いただけるものとOSPOに相談してもらうものを明確に分けて対応しています。OSPOと法務が協力して、事前にガイドラインやチェックフローなどで明文化したり、わかりやすい具体事例を共有したりすることで、個別に相談しなくてもサービスや事業側が安心して企画開発に取り組むことができる範囲を増やせているのではないかと考えています。
法務として、こうしたスピーディーかつ適切にコンプライアンスを遵守できる仕組みづくりを実現することで、法律面を意識しなくても自然に法的合理性が担保され、社会に貢献できるサービスやプロダクトが、迅速かつ安全にリリースできるようになればと考えています。
これからも、技術と法律の橋渡し役として、イノベーションを阻害せずに法的要件を満たすための新たなアプローチを模索し続けたいですね。そして、社内外のステークホルダーと協力し、ユーザーにとって本当に価値あるサービスを提供することが、私たちの目標です。
取材日:2025年1月27日
文:大矢 幸世
記事中の所属・肩書きなどは取材日時点のものです。
「WHY? LINEヤフー」バックナンバー

- LINEヤフーストーリーについて
- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。
コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。


