LINEヤフーのマーケティングソリューションを扱う部門の中で、広告代理店とのパートナーシップに特化した営業組織です。
LINE広告やYahoo!広告、LINE公式アカウントなどのサービスを代理店を通じて市場やクライアントに届けるために、ビジネス開発や営業支援、販売活動のサポートなどを行なっています。
もともと旧LINEと旧ヤフーそれぞれに存在していた広告代理店向けの組織が、合併を機に一つに統合されて生まれました。

2023年10月、LINEやヤフーをはじめとする5社が合併し、LINEヤフーとして新たなスタートを切りました。異なる歴史やカルチャーを持つ組織がひとつになることを目指し、各組織でさまざまな取り組みが行われてきました。
今回話を聞いたのは、広告代理店の営業組織であるコーポレートビジネスカンパニー(CBC)のマーケティングパートナー本部のメンバーです。合併時、どんな課題に直面しそれをどう乗り越えてきたのか。そして今、どんな組織として進化しているのか。合併から約2年、現場で生まれた変化と、それを支えた文化について語ってもらいました。




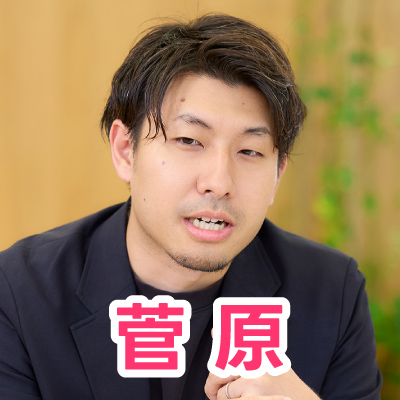
LINEヤフーのマーケティングソリューションを扱う部門の中で、広告代理店とのパートナーシップに特化した営業組織です。
LINE広告やYahoo!広告、LINE公式アカウントなどのサービスを代理店を通じて市場やクライアントに届けるために、ビジネス開発や営業支援、販売活動のサポートなどを行なっています。
もともと旧LINEと旧ヤフーそれぞれに存在していた広告代理店向けの組織が、合併を機に一つに統合されて生まれました。

旧LINEは、すごく風通しがよくて、社歴関係なく自由に意見を言える空気がありましたね。新卒でも萎縮せずに発言しやすい環境だったと思います。入社前に内定者アルバイトをしていた頃からその空気感は感じていました。

旧ヤフー側も、すごく似た雰囲気でした。先輩が丁寧に見てくれて、若手が「これやりたい」と言うと「いいね、やってみよう」と背中を押してくれる自由なカルチャーがありました。


そうですね。ですので、合併しても「カルチャーが違ってやりにくい」みたいなことは、あまり感じなかったです。
合併前に、同じ代理店を担当する旧LINE、旧ヤフーのメンバーで情報共有する機会もありましたし、先輩方が主導して両社の交流の場を何度か開催してくれて。そういった場で顔と名前がわかっていたことで、合併後もあまり壁を感じずにコミュニケーションが取れたなと思っています。

僕は合併のタイミングでリーダーになり、旧LINEと旧ヤフーのメンバーが所属する混合チームを見ることになりました。お互いの顔は知っていても、価値観や仕事のスタイルはどうなんだろうと不安はありましたね。
それに、それぞれが扱ってきたプロダクトが違うので、ナレッジの差や理解度のばらつきをどう埋めていくかという課題もありました。

私もちょうど合併のタイミングで今の部署に配属されました。LINEとヤフー、両方のプロダクトを同時に学ぶ必要があって、正直かなり大変でした。情報量も多く、アップデートのスピードも早いですし、それぞれの商品の良さを理解してどう営業していくか、今でもすごく難しいと感じる部分ですね。


LINE出身の先輩も、ヤフーの検索広告はLINEにはないタイプのプロダクトだったので、知識がない中でそれをいきなり営業するというのは不安だった、という声をよく聞きましたね。
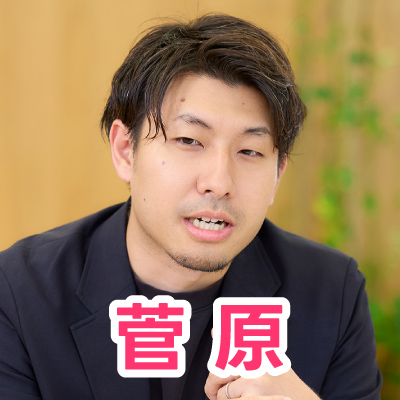
顧客接点部門として、プロダクトに対するナレッジの格差は重要な解消ポイントだと考えていました。
具体的には、部門横断の合同slackグループを立ち上げて、Tipsの共有や「こんな時どうする?」「これはどういう機能?」というプロダクトの不明点を誰でも気軽に質問できる環境を作りました。
このグループがすごく盛り上がって、日常的に質問やナレッジが飛び交っていて、勉強会の開催にもつながっていきました。

私たちの本部では「フェス」と呼んでいたのですが、Yahoo!広告やLINE公式アカウントなどのプロダクトごとにブースを設け、自由に参加できるナレッジ共有会も行われました。オフラインで顔を合わせながら学べる場だったので参加ハードルも低く質問もしやすかったと思います。

名前の通りカジュアルな空気感があって、でも中身はしっかりと学びにつながる場だったので、参加者からも好評でしたね。

ツールの権限周りも問題でした。BoxやSlackが見られなかったり、旧LINE、旧ヤフー間で互いのツールにアクセスできない状況が続いていて、必要な情報にたどり着けないことがありました。それで、知識やできる業務に偏りが出てきてしまって、メンバー同士で摩擦が起きることもありました。

現場から「このツールが見られない、使えない」といった声を随時、菅原さんの営業推進部に共有していました。
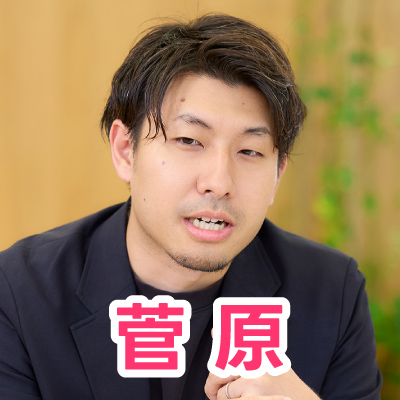
その依頼を受けて、部長陣や営業推進部のメンバーが毎週のミーティングで、どのツールが使えなくてどの業務に影響しているのかを一覧化して、関係部署と連携しながら解決していきました。ツールごとに「いつ頃解消できるのか」のロードマップを敷いて、現場にも共有していました。

こうした現場からの改善の声は、100件以上あがっていたと思うのですが、全てスピード感を持って対応していただいていた印象です。
それに、「今は使えないけど来月には解決される」といった見通しがあったことで、「じゃあ今は別のツールでこの業務を進めておこう」といったコミュニケーションができたので、リーダーとしてはすごく助かりました。
そうすると、自然と今できることを伸ばしていこうとする動きが生まれ、メンバー同士でもお互いを補い合う姿が広がっていきました。助け合いながらチームとしても成長していったように感じます。
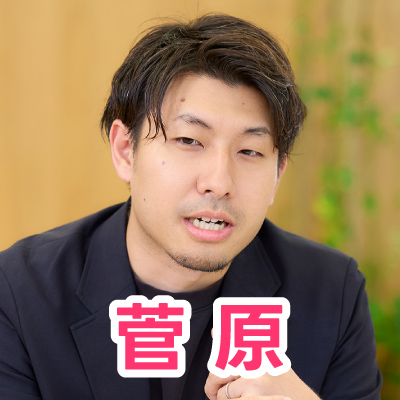
そうですね。外から見れば、旧LINEも旧ヤフーも関係ない「LINEヤフー」のプロダクトなので、「内部の事情で代理店やクライアントに迷惑をかけるわけにはいかない」という意識が本部全体の中に共通であったように思います。
だからこそ、「お互いの会社に新入社員として入社したつもりで、ゼロからお互いに学び合おう」というスタンスで、役職や社歴を問わずナレッジ共有が進んでいったと思います。

まさにそうですね。僕は山田さんが新卒入社した時のメンターだったんですが、今では山田さんや他のメンバーに教えてもらうことも多いです。本当に頼もしいですね。

誰にでも相談しやすい雰囲気はすごくありますよね。分からないことがあっても「いったんLINE出身のあの同期に聞いてみよう」「あの先輩はこのプロダクトに詳しそう」と思えるこの環境がすごくありがたいと思っています。「お互いに助け合って乗り越える」という感覚で、今もナレッジ共有や相談をし合っています。


僕も「助け合う」という文化はすごく感じています。この4月に部署異動して、これまでと全く違う業務を担当することになったのですが、もともとその業務をしていた同期がずっとサポートしてくれていて。心強いですし、こういう文化がある組織でよかったなと思います。
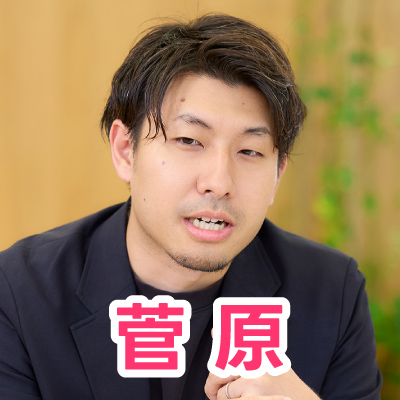
マーケティングパートナー本部の本部長からも、「旧LINE・旧ヤフーという呼び方はやめよう」「As One(一丸となって)で進もう」というメッセージが繰り返し発信されていました。組織としても、そのメッセージを軸に意識的に文化づくりに取り組んできたと感じています。


「Flat・Fun・Future(先進的)」というスローガンもあって、上下や出自にとらわれないフラットな関係性が生まれ、助け合いや相談のしやすさにつながっていると思います。

私の所属するパートナーセールス3部は、週1回が必須の出社日ですが、自主的にそれ以上出社しているメンバーも多いです。私は毎日出社していて(笑)、顔を合わせて一緒に働くことで、メンバーとの仲はかなり深まっていると感じています。

僕も寂しがり屋なので、みんなに会いたくてほぼ毎日出社しています(笑)。
特に僕のチームは若手が多いので、一緒に仕事をして疑問が出たらその場で解決させるというのを意識しています。逆に1on1をスキップする時もありますね。もちろん1on1も大事なんですが、対面で即時のやり取りができる環境は業務のスピードや質にも影響していると思います。


僕も新卒で入社して以来、オフィスに来ればすぐ聞ける先輩や同期がいるという環境にすごく助けられています。メンバーと話すことでリフレッシュにもなりますし、みんなが頑張っている姿を見ると、モチベーションにもなります。
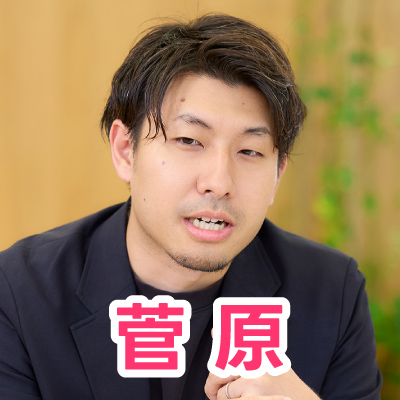
半年に一度、営業本部内で表彰制度を実施しています。営業成績だけでなく、Tipsの投稿やナレッジのシェアなど、組織への貢献も評価にしています。また、営業成績や顧客満足度に繋がるアクションテーマやプロダクトを設定して、部やチームで競う形式の表彰もあります。
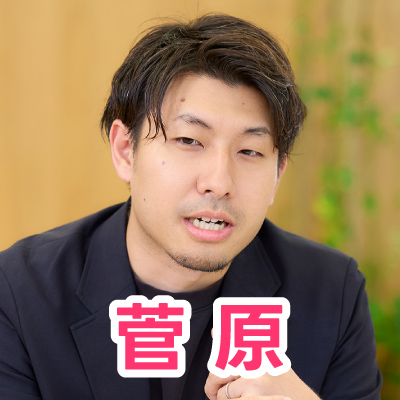
はい。ただ、合併して扱うプロダクトも代理店の規模も増えたので、いかにフラットに評価するかは、毎回頭を悩ませている部分ですね。代理店の規模やプロダクトの性質に応じたリーグ制を導入したりして、できるだけ公平に切磋琢磨できるよう工夫しています。

めちゃくちゃ取り入れてくれていますよ。現場から毎回いろんな意見を上げていますが、それに対してちゃんと耳を傾けて、毎回改善されている感覚があります。
正直、「全員が100%納得できる評価制度」を作るのはすごく難しいと思いますが、それでも毎回現場の意見を踏まえて工夫をしてもらえるのは、現場としてすごくありがたいです。
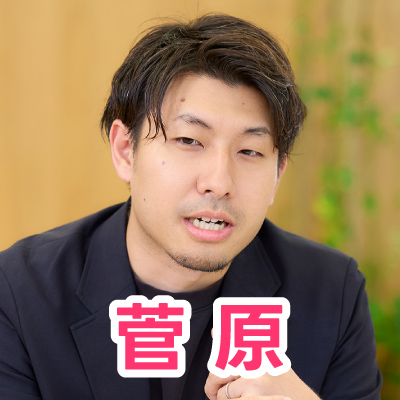
組織として、「頑張った人を公平に讃える文化」をもっと根付かせていきたいんです。よく「組織の2:8の法則(優秀層2割が成果を引っ張る)」と言われますが、その2割にどんどんメンバーを押し上げていきたいという気持ちがあります。そのためにも現場の声を反映しながら、納得して前向きに参加する制度を作っていきたいと思っていますね。


私は、半期において本部内で最も活躍・貢献した入社3年以内の社員に与えられる「新人賞」の表彰をいただいたことがあります。自分の取り組みをしっかり見てもらえているという実感が持てて、すごく嬉しかったです。大きな場で表彰される機会もなかなかないので、自信にもなりました。

僕はまだ表彰されたことはないのですが、身近な先輩や同期が評価されているのを見ると、「成果を残していてかっこいいな」「自分もあんな風になりたい」といい刺激になっています。

評価の基準が明確なので、「表彰されるために自分が何を頑張ればいいか」がイメージしやすいと思います。それが自然と日々のアクションにもつながり、いい意味でライバル意識も生まれて、刺激し合いながら成長できる。良い仕組みだなと思いますね。

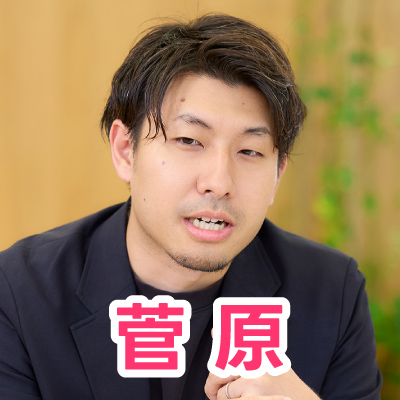
合併によって組織は大きくなり、意思決定のスピードや調整の難しさといった課題も感じることはあります。ただ、それは個人としても組織としても「乗り越えるべき成長のチャンス」だと捉えています。
正直、まだナレッジの格差があったり、完全に組織融合ができているとは言えない部分もあります。それでもこれまで積み重ねてきた取り組みによって、少しずつ融合が進んでいる実感があります。
たとえば、wevox(※)のデータでは、私たちの部は「人間関係」の項目が特に高評価です。上司や同僚との関係性や、周囲への相談のしやすさといった人とのつながりをしっかり築けている証だと思います。この土台があるからこそ、これからもいろいろな課題を乗り越えていけると感じています。
※ 従業員のエンゲージメントや組織の状態を可視化するツール

入社2年目になり、LINEヤフーの幅広いプロダクトや機能について理解が深まってきました。これだけ多様なサービスやデータを扱える会社にいるからこそ、それらをクライアント支援にきちんとつなげていきたいです。
CBCでも、議事録作成や資料づくり、壁打ち、営業準備など、日々の業務でAIを使うことが当たり前になりつつあります。僕自身、社内のAI活用を推進するエバンジェリストとして、これまでに講座や活用事例の共有などを通じて、チーム内外への浸透を図ってきました。
今後も一つでも多くの成功事例を生み出せるよう、AIを味方につけながら自分のスキルも高めて、もっと価値のある提案ができる営業を目指していきたいと思っています。


今では、LINEとヤフー両方のプロダクトを横断して提案するのが当たり前になっています。ただ、代理店やクライアントからはまだ別会社のものとして認識されることも多く、そこに少し悔しさも感じています。
これからは「LINEヤフー」として評価してもらえるように動いていきたいです。データやプラットフォームの統合が進み、できることがますます増えている今だからこそ、「LINEヤフーならではの提案」をしっかり形にできるセールスを目指していきたいと思っています。

植田さんも言っていますが、生成AIのおかげで日々の業務だけでなく、営業の質も向上しています。
ただ、生成AIは基本的には「過去の延長線上にある答え」を出すのが得意なツールです。一方でLINEヤフーが今取り組んでいるのは、前例のないチャレンジばかりです。プロダクトを掛け合わせた新提案や、驚かされる取り組みがどんどん増えています。
これからは、AIも活用しながらも、ヒアリングや課題の言語化といった「人にしかできないこと」に価値を出していくべきだと思っています。そうした「答えのない問い」にしっかり向き合っていくことが、僕たち営業の役割だと感じています。
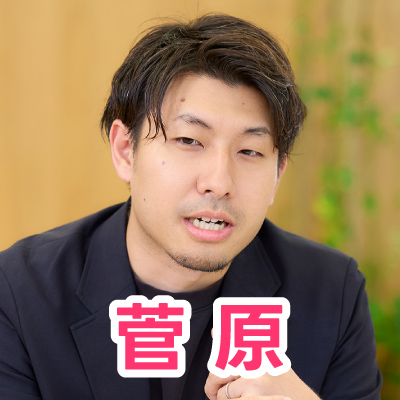
合併によって、提供できるサービスや実現できることの幅は確実に広がりました。トップ層からもその可能性は繰り返し伝えられていますが、現場ではそれぞれが個別のプロダクトや業務に向き合っているので、それを実感しにくい瞬間もあります。
それでも、代理店やクライアントと接する中で、「うちってまだまだ成長できる会社なんだ」と感じる瞬間も増えてきています。だからこそ、個々の動きが「点」であっても、無限の可能性を感じながら前向きに成長していけると本気で思えるような組織にしていきたいですね。
そういった集団になることで、まずは人から頼られ、プロダクトも良くなっていくと信じています。最終的には「LINEヤフーに相談するのが一番だ」と思ってもらえる、そんな頼られる組織、会社をつくっていきたいです。


「真心はいつか必ず通じる」AI戦略を担うCPO慎がいま大切にしたいこと

「AIをパートナーとして共に成長する」生成AI役員、宮澤が描く未来

「全社員でユーザーの安全を守る」CISO仲原が目指す、LINEヤフーのセキュリティ
取材日:2025年7月15日
文:LINEヤフーストーリー編集部 撮影:猪又 直之
※本記事の内容は取材日時点のものです
