これまで自分には関係ないと思っていましたが、スマホ1台で被害に遭う危険性が潜んでいることを実感しました。SNSで「すぐに稼げる」などのDMが来たら、ブロックや通報を行い、連絡は無視するよう心掛けたいと思います。
これから夏休みに入り、友達と遊ぶためのお金が必要な場面が出てくるかもしれないですが、甘い言葉に惑わされず、安全な場所で働くことを意識したいです。

子どものネット利用が増える夏休み。闇バイトなどネットにまつわる事件が社会問題化するなか、「うちの子は大丈夫?」「ネットのトラブルに巻き込まれないか不安」と感じている保護者の方も多いのではないでしょうか。
今回、夏休みを前に、LINEヤフーが学校で実際に行った「情報モラル教育」の授業から「闇バイト」にフォーカスして、ご家庭での注意点、声かけのポイントなどをまとめました。
毎年7月は「青少年の被害・非行防止全国強化月間」です。家族で話し合うきっかけに、ぜひご活用ください。

いわゆる「闇バイト」とは、法的に問題のある業務や違法な手段で収入を得るような仕事を指します。特に中高生は社会経験が浅く、「短時間で高収入が得られる」など、SNS上での甘い勧誘に巻き込まれやすいリスクがあります。
背景には経済的な事情や家庭環境が影響しているケースも少なくありません。なかには、「悪いとわかっていてもお金が必要」だとか、「未成年なら罪は軽いはず」という誤った思い込みで関与する例もあります。
さらに言葉巧みに勧誘されて、加担していると気づいた頃には弱みを握られて、抜け出せなくなっている、そんな深刻なケースも報告されています。善悪の判断や情報モラル教育だけでは回避しきれない、非常に難しいテーマです。

大きな背景の一つにはSNSが強く影響していると考えています。中高生はSNSとの接触は非常に多いですから、「高収入・簡単・バレない」といった甘い勧誘ダイレクトメールなどが簡単に届いてしまうのです。
犯罪者側も、そこを狙っているのですが、未成年の場合、「これなら、大丈夫だろう」と軽く考えてしまうリスクがあります。
警察庁の最新統計によると、2024年の特殊詐欺で検挙された受け子1409人のうち、約20%が少年で、受け子になった経緯の約42.7%が「SNSからの応募」でした(※1)。
また、勧誘方法も複雑化、多様化していて、真面目な学生の善意が逆手に取られることで、巻き込まれてしまうケースなどもあります。
※1:警察庁「令和6年における特殊詐欺の検挙状況等(暫定値)」

こうした変化を感じたら、頭ごなしに問いただしたり怒ったりするよりも対話をしてほしいですね。まずは、「心配しているよ」「力になりたいよ」という姿勢を伝え、万が一、怪しい状況を察知した際は、脅迫を受けている可能性も念頭に、#9110(警察相談専用窓口)や学校に早めに相談しましょう。
#9110は、110とは異なり、電話をかけた地域を管轄する警察につながる相談窓口で、犯罪や事件に当たるのかまだわからないものの、闇バイト、ストーカーなど、警察に相談したい時に適した番号です。
技術的には以下、2つの仕組みがあります。
| 手段 | 概要 | 注意点 |
|---|---|---|
| フィルタリング | 有害サイトやアプリを自動ブロックする仕組み。 携帯会社や専用アプリで設定可能。 |
高校生になると解除方法を調べて回避することも珍しくない。 |
| ペアレンタルコントロール | 利用時間・課金・アプリ権限を保護者が管理できる機能。 端末設定や家庭用ルーターで調整可能。 |
子どものほうが親よりも機器操作に長けていることが多く、設定をすり抜けられるケースも。 |
ただ、子どもが闇バイトに関わるネットとの接点を技術的にブロックすることは非常に難しい現実があります。
スマホに慣れた世代で、テクノロジーに精通している子どもたちは、ペアレンタルコントロールやフィルタリングも簡単に回避してしまいます。
だからこそ大切なのは、日頃の信頼関係ではないでしょうか。私自身も一人の親として、子どもを丁寧に理解してあげることを意識しています。子どもたちが仮に間違いをしてしまったとしても、否定せずに、しっかり耳を傾けてあげたいですよね。
そのためにも、「怒られるかもしれない」「親には伝えられない」と思わせない雰囲気が、相談の第一歩になるはずです。
また、いざという時の相談先、例えば、先ほどお伝えした警察の専用窓口番号(#9110)などを家族のルールとして認識、明示しておくことも、ひとつの対策です。

7月14日に実施された東京都立第一商業高校(東京都渋谷区)での情報モラル教育講座の様子。当日は、「闇バイト」に加え、「フィッシング詐欺」と、2つのテーマで講義を実施した
はい。私たちは、この問題に向き合い、子どもたちが巻き込まれないようにするため、小中高生を対象に、「情報モラル教育」を全国の学校で定期的に実施し、ネットの正しい使い方やトラブル回避のための考え方を伝えています。また、静岡大学と共同で中高生向けの教材開発も行っています。
授業は「正しい答えを教える」のではなく、「自分で考える」力を育てることを目的にしています。具体的には次の3つのワークを組み合わせています。
1.「自分が闇バイトをやってしまうかもしれない」と想像する
2.加害者側の立場になり、どんな言葉で勧誘するかを考える
3.闇バイトのシナリオをもとに、「誰に・いつ相談できたか」を考える
このように、善悪で線引きするのではなく、「その状況に自分が置かれたら?」という視点で、判断力と想像力を育む構成にしています。

授業後のアンケートで「私は絶対やらないと思っていたけれど、自分にも巻き込まれる可能性があると感じた」という声を複数の生徒からもらいました。
自分の身にも起こり得ると気づく瞬間が、一番の学びになっていると感じます。

これまで自分には関係ないと思っていましたが、スマホ1台で被害に遭う危険性が潜んでいることを実感しました。SNSで「すぐに稼げる」などのDMが来たら、ブロックや通報を行い、連絡は無視するよう心掛けたいと思います。
これから夏休みに入り、友達と遊ぶためのお金が必要な場面が出てくるかもしれないですが、甘い言葉に惑わされず、安全な場所で働くことを意識したいです。

今まで闇バイトやフィッシング詐欺という言葉はニュースで聞く程度でしたが、授業で詳しく話を聞いたことで意識が変わりました。これからは自分事として情報を集めて、「詐欺かな?」と思うようなメールが届いても安易にURLを開いたりせず、「まずは疑ってみる」という選択を取ろうと思います。
また、もし不安に感じることがあったら、まずは身近な大人や警察に相談することが大切だと感じました。
狙い通りの成果につながっていて、嬉しいですね。やはり、闇バイトは、なんとなくみなさん、認識されているのですが、それを自分ごとにするのってなかなか難しい課題なのですよね。
夏休みを前に実施できてよかったですし、生徒はもちろん、お父さんやお母さんなど、まずは、多くの皆さんに自分ごと化してもらえたらと思っています。
インターネット、SNS、AIなどの技術は私たちの身近な世界そのものになりました。だからこそ、WOWで!な体験を創出しつつ、安全・安心な利用環境を整える。この両立が私たちの使命です。
教材開発や出前授業などを通して、技術の表裏を正しく伝え、リスクを軽減する取り組みを続けていきます。開発した教材は、LINEヤフーのサイトでも一般公開していて、こちらはぜひ親子で一緒にご覧いただき、多くの方に活用してもらえたらうれしいですね。
また、未成年への教育だけでなく高齢者まで含めた世代横断で、誰もがインターネットの恩恵を安全に享受できる社会を目指して、今後もさまざまな取り組みを実践していきたいと考えています。
闇バイト防止教育に関する教材をこちらのページからダウンロードできます
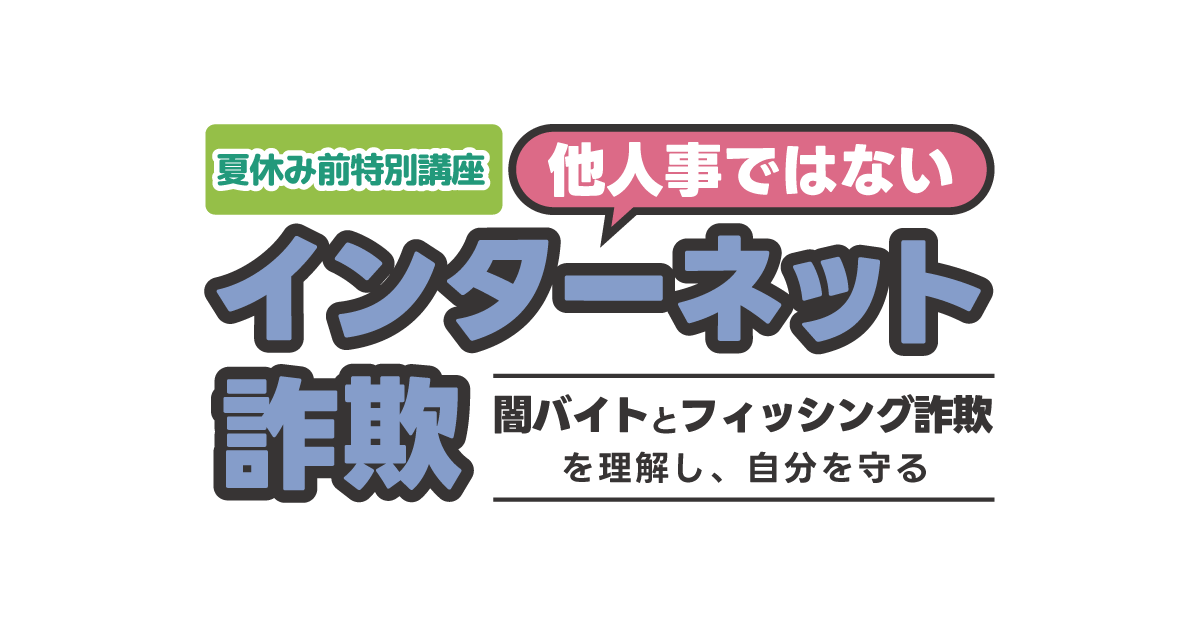
LINEヤフー、サイバー犯罪の危険性が高まる夏休みに備え、東京都立第一商業高等学校にてインターネット詐欺対策の特別講座を実施

スマホ世代の情報モラル教育 誹謗中傷から子どもを守る方法は?

子どものネットリテラシー、どう育てる? LINEみらい財団と考える「楽しいコミュニケーション」
取材日:2025年7月14日
文:LINEヤフーストーリー編集部 撮影:黒川 大輔
※本記事の内容は取材日時点のものです
