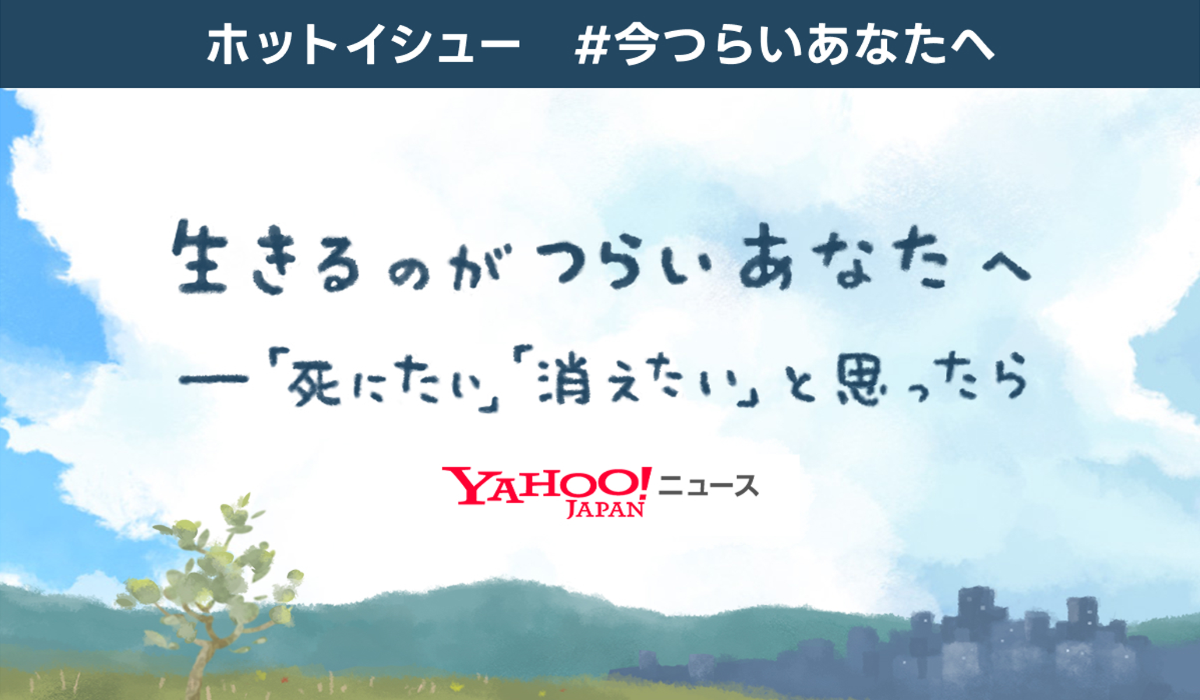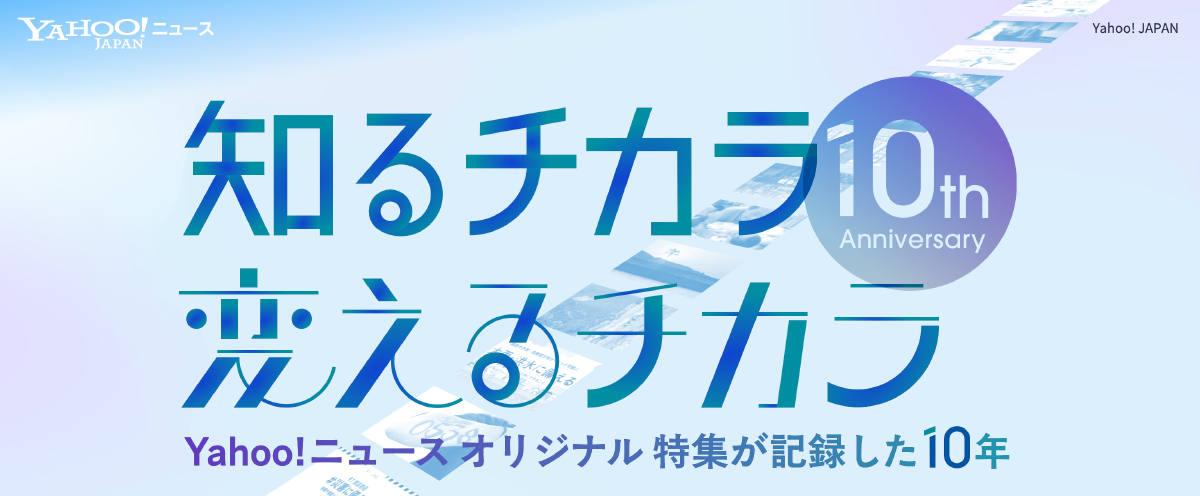「言葉にできなかった声を届けたい」Yahoo!ニュース オリジナル 特集 10周年の軌跡とこれから
いま注目を集めるトピックから見過ごされがちな社会課題など、幅広いテーマを独自の視点で取材・編集している「Yahoo!ニュース オリジナル 特集(以下、特集)」は、2025年9月で10周年を迎えました。
節目の年を迎えた今、10周年の軌跡や取り上げてきた社会課題、ユーザーからの反響などについて、特集のプロジェクトマネージャー高山と編集の塚原に聞きました。
もっと見る
高山 千香(たかやま ちか)
ヤフーニュース・リアルタイム検索本部 オリジナルコンテンツ部
塚原 沙耶(つかはら さや)
ヤフーニュース・リアルタイム検索本部 オリジナルコンテンツ部
なぜオリジナルコンテンツが必要だったのか
――特集は、どのような経緯で立ち上がったのですか?
高山:
そこで、Yahoo!ニュースとして、ユーザーのみなさんに読みごたえのあるルポ記事や調査報道、社会に埋もれる課題を深く掘り下げたコンテンツを届け、「ここには他にはないものがある」 と思っていただきたいという思いがありました。
また、社内のメンバーが、英国放送協会(BBC) を訪れる機会があり、刺激を受けたのも大きなきっかけでした。そのときに立てたゴールが3つあります。
一つ目は、世の中の課題を拾って深掘りし、課題解決の糸口を提供する こと。外部からも評価されるメディアになる こと。三つ目はYahoo!ニュースのブランドリフトに貢献する こと。
これらを実現するために、特集は始まりました。
――そこから、どのようなテーマを発信してきたのでしょうか?
高山:
高山:
たとえば、2021年にホットイシュー「#今つらいあなたへ」を立ち上げ、つらい気持ちを抱える人に寄り添うコンテンツの発信を始めました。
同じ年には「#性のギモン」もスタートし、人間関係や体の悩み、性教育や性被害など、幅広い視点から「性」にまつわる課題を取り上げています。
高山:#こどもをまもる 」、東日本大震災の被害の風化を防ぐための「#知り続ける 」など、10以上のホットイシューを展開し、社会の課題をさまざまな視点から取材・発信 し続けています。
10年伝えてきた社会課題とユーザーの反響
――これまでの活動で、印象に残っていることやユーザーからの反響を教えてください。
塚原:「性教育は必要だと思う」「社会がこう変わってほしい」といった肯定的な声が多く寄せられた のです。
Yahoo!ニュースのコメント欄(以下、ヤフコメ)上で建設的な議論が生まれ、これはもっとさまざまな視点から深く取材・制作していくべきテーマだと感じました。ユーザーの声に後押しされ、ホットイシュー「#性のギモン」として継続して取り組むことになりました。
――「性教育」というテーマを、どう掘り下げていったのですか?
塚原:
包括的セクシュアリティ教育は、人権と多様性の考え方を土台に、人間関係、ジェンダーの理解、体の仕組み、自分や相手の安全の確保など、より広い視点で「どう生きるか」について学ぶものです。私たち自身も、その背景や意義を理解した上で記事を届けたいと考え、まずは社内で理解を深める ところから始めました。外部の識者を招いて社内勉強会を行い、知識を得て、目線を合わせてから制作に取りかかりました。
その後は、外部のジャーナリストや記者、ライターの方々と協力し、教育現場のルポ、親子の悩み、妊娠・出産、ジェンダー、月経や更年期などの体の不調、性暴力や性犯罪など、多くの記事を「#性のギモン」で制作してきました。
――こうした記事に対して、どのような反響がありましたか?
塚原:経口中絶薬をテーマにした連載 が科学ジャーナリスト賞を受賞したり、男性の性被害を扱った記事 が 「Internet Media Awards 2023」の選考委員特別賞を受賞するなど、外部からの評価をいただいたこともあります。また、柔道のルールに関する問題を取り上げた1年後には、全日本柔道連盟のルールが改定されたりするなど、社会の関心を呼び、変化につながる記事を届けられたと思っています。
塚原:「今まで人に言えなかったけれど、この記事を読んで初めて自分の体験を書き込めた」 というコメントをしてくださる方もいて、センシティブなテーマだからこそ、ウェブで発信することに意味があったのではないかと感じました。
そうした本音や体験を語ったコメントに対して、ほかのユーザーが共感や励ましの言葉を返す様子も見られました。取材に応じてくださった方々の勇気が、ユーザーに共鳴して広がっていったのではないか と感じています。
――そのほか、どのような取り組みを行っていますか?
高山:ビジュアルで知る 」の取り組みを行っています。
その一つとして、学校に行きたくない子どもに向けたコンテンツ「学校行かないとダメですか? 」では、公開直後から大きな反響がありました。記事に設置したLINEの相談窓口「ユキサキチャット 」に、約100件の相談が寄せられた のです。普段ニュースを見ない層にも届けられた手応えがありましたし、漫画を使うなど表現を工夫することで子どもにも読んでもらえたことが大きな意味を持ったと感じて います。
また、長期休み明けは「学校に行きたくない」などと訴える子どもが増える時期でもあります。翌年には、いじめをテーマにしたコンテンツ「いじめ そのときできることは?」を制作し、Internet Media Awardsのソーシャルグッド部門で受賞しました。発信の広がりを実感できた事例の一つです。
塚原:
編集部が守り続けたもの、取材で大切にしてきたこと
――こうしたコンテンツは、どのように作り上げていくのでしょうか?
塚原:新規性・時事性・関心度 を重視し、誰か一人の判断ではなく、社内外で議論を重ね、合議制で決めていくのが特徴です。取材にも時間をかけていて、特にルポ記事であれば複数箇所を取材して、多面的に構成 するようにしています。
――制作を進めるにあたっては、どのようなことを意識していますか?
塚原:取材で得た客観的なファクトをきちんと伝える ことに重きを置いています。
ユーザーにできるだけ分かりやすく伝えるため、原稿は公開までに編集部内の複数人で読み、内容を確認しています。編集部のメンバーは、新聞、テレビ、出版、ITなど、さまざまな業界の出身者がいて、異なる視点からの意見があがることもしばしばあります。また、外部の校閲者にも必ず見ていただいています。
インタビューなどでは、多くの場合、取材対象者に寄り添った、いわば「隣人」のような目線でお話を伺う ことを意識しています。ユーザーに「自分もこの人の話を聞けた」と感じてもらえるように、「仲介者」として丁寧に言葉を届けたい と考えています。
――多くの社会課題を取り上げる中で、テーマの選び方やユーザーへの届け方など、悩むこともあるのではないでしょうか?
塚原:「なぜ今これを取り上げるのか」「今このテーマをどう伝えるべきか」 を議論しています。同じ取材対象や事象を扱う場合でも、切り口や視点に新しさを出せるように、社内外でよく話し合っています。
また、その記事を届けたい人に辿り着いているのかどうか、なかなかわからないものです。同じテーマを一度きりではなく、繰り返し届けていく必要がある と思っています。社会課題は無数にありますし、「声をあげにくいこと」「見えづらいこと」をどのように見つけるかも難しいですね。
だからこそ、さまざまな関心や視点を持つ方々や専門性のある方々と一緒に取り組んでいきたいと思っています。そうした書き手の方々に「ここで書きたい」「このテーマに一緒に取り組みたい」と思っていただけるような場でありたいと考えています。
――LINEヤフー社内でAI活用が進む中、特集ではどのようにAIを活用していますか?
高山:現場に足を運び、一次取材をしっかり重ねていること です。これまではそうした取材素材をもとに1本のテキストや動画を作るというのが基本でしたが、生成AIを活用することで、得られた素材を別の形に加工したり、多言語化したりすることが可能になってきました。
たとえば、今年の8月には、取材記事から音声コンテンツを制作するテストを行いました。普段Yahoo!ニュースを読んでいない方にも届けられた手応えがあり、コンテンツの届け方に新しい可能性を感じています。
今後も、これまで通り現場での取材を大切にしつつ、動画・音声・多言語など、さまざまな形で、取材で得た声や空気をより広く伝えていきたい と思っています。
これからの挑戦
――今後、新たに取り組みたいことを教えてください。
塚原:興味を深められたり、今起きている出来事をより深く知るきっかけになったりするような仕組みを考えていきたい です。「ホットイシュー」もその一つですが、シリーズ化して継続的に発信し、2本目、3本目と読んでいくうちに、課題の全体像を理解でき、多面的に捉えられるようにしたいと思っています。
入り口は1本の記事でも、そこから関心の広がりや奥行きを作っていく。
それによって特集の枠を超えて、ユーザーの行動につながるコンテンツを目指してしていきたいです。
10周年を迎えた今、伝えたいメッセージ
――最後に、ユーザーに向けてメッセージをお願いします。
高山:社会の中で見えづらい声やテーマを、少しでも多くの人に届けるために、これからも一つひとつの記事に向き合って いきます。
これまでの10年の活動を通して、冒頭でお話しした3つのゴールも、少しずつ形にできてきたと感じています。
一方で、まだまだ課題もあります。Yahoo!ニュースでオリジナルコンテンツを作っていることは、まだ十分に知られていないとも感じています。たくさんのコンテンツパートナーの記事と一緒に私たちの
ドキュメンタリー や
RED Chair などがあります。ぜひYahoo!ニュース発のさまざまなコンテンツがあることを知っていただきたいです。
そして、他のメディアと協力して社会課題を伝えるとともに、Yahoo!ニュースならではの切り口も楽しんでいただけたらと思います。最終的には、私たちのコンテンツが「知ること」の入り口となり、行動や対話が生まるきっかけになれたら、とても嬉しく 思います。
Yahoo!ニュース オリジナル 特集10周年 特設サイト
Yahoo!ニュース オリジナル 特集10周年 特設サイトです。社会課題に向き合ってきた10年の歩みと、著名人・専門家・記者によるコメント、記念プレゼントなどを紹介しています。ぜひご覧ください!
「知るチカラ、伝えるチカラ〜Yahoo!ニュース オリジナル 特集が記録した10年〜」
取材日:2025年9月3日
LINEヤフーストーリーについて
みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。