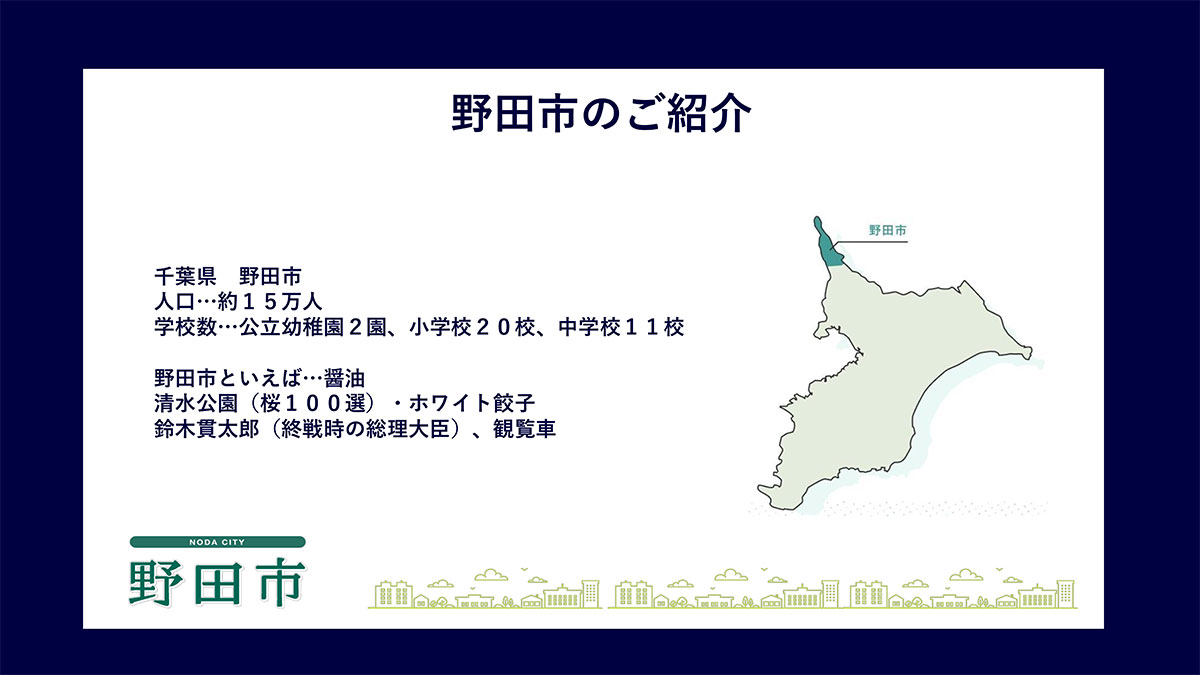千葉県野田市の挑戦 教育DXを進める「LINEスクール 連絡帳」導入の舞台裏

先生の長時間労働が社会問題(※1)となる中、教育現場の負担のひとつが保護者との連絡です。電話での欠席連絡や紙のプリント配布は時間も手間もかかり、情報の行き違いにつながってしまうことも。
こうした課題を解決するために誕生したのが 「LINEスクール 連絡帳」です。欠席連絡やお知らせ配信、安否確認まで、LINEひとつで完結できます。
サービス開始から7カ月で300校以上に導入いただき、教育DXの新しい潮流となりつつあります。
そこで今回は、その背景や開発者の思い、LINEスクール 連絡帳を市内33校すべてに導入いただいた千葉県野田市教育委員会の実践事例をお届けします。
※1:デジタル庁 教育DXロードマップ
- 木之下友城(きのした ゆうき)さん
- 野田市教育委員会指導課指導主事
野田市内の中学校で保健体育や社会科の教員を務めた後、教育委員会へ出向して2年目。
- 黒田望(くろだ のぞむ)
- LINEヤフー CBカンパニー 事業開発部教育チーム リーダー
法人事業領域にて営業、戦略プランナー、事業企画を経験後、LINEスクール 連絡帳を新規事業として立ち上げた。
- 尾勢瑛美(おせ えみ)
- LINEヤフー CBカンパニー事業開発部教育チーム
元保育士。LINEスクール 連絡帳の企画・セールス担当として、自治体への提案を行っている。
教育現場の課題とLINEスクール 連絡帳が生まれた背景
――まずは教育現場の現状と課題について、木之下さんにうかがいたいと思います。
昨年度までは紙や電話など、アナログ的な対応が多かったのが実情です。保護者宛の文書は印刷して生徒に手渡すのが一般的でした。
学校によっては無料で使える連絡アプリを導入していることもありましたが、野田市として統一ルールはない状況でした。無料プランには配信数などの制限があり、結局は紙での配布になりがちなケースが多かったのです。
また、遅刻、欠席、早退などの連絡も電話が多く、朝から対応に追われる先生も少なくありませんでした。全国で働き方改革が叫ばれる中で、野田市も例外ではなく、DX推進は大きな課題になっていたのです。
――そうした現場の課題を、黒田さんたちはどのように解決しようと考えたのですか?
3年ほど前から教育領域においてLINEヤフーに何ができるのかを探る中で、まさに私は、誰もが通る学校という場所の重要性を認識しました。そして、先生方や保護者の皆さまからお話を聞く中で、コミュニケーションの領域において「既存のツールでは解消できていない大きな負がある」と強く感じました。
「コミュニケーションを生業とするLINEヤフーとしてこの課題を放っておくわけにはいかない」。そんな思いで事業化を進め、教育領域で実績の豊富な外部パートナーであるエースチャイルドさんの協力もあり、2025年1月にリリースさせていただきました。

――野田市はどのようなプランで導入したのですか?
2025年4月から市内の全33校で、ベーシックプラン(※2)を導入しました。小学校が20校、中学校が11校、公立幼稚園が2園です。
ちなみに野田市は人口が約15万人。千葉県の西の端、チーバくんの「お鼻の部分」にあたります。お醤油の名産地として知られています。
※2:2026年3月末まで無償提供中
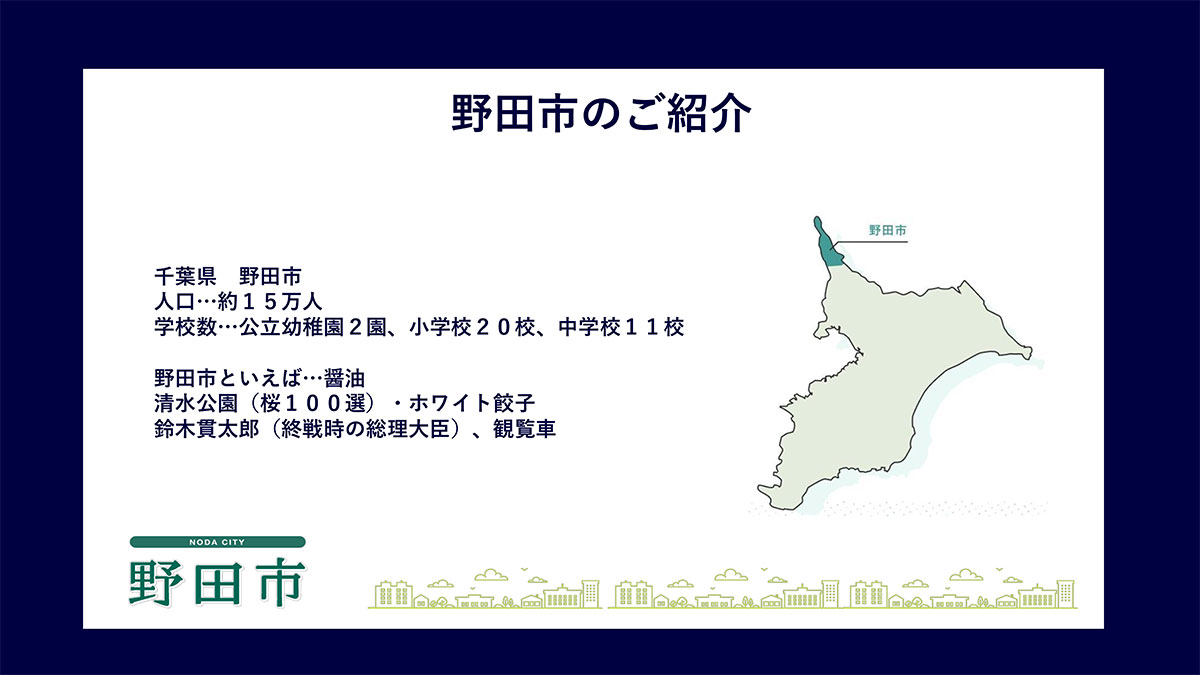
野田市公式サイト
――尾勢さん、LINEスクール 連絡帳にはどんな特徴があるのですか?
LINEスクール 連絡帳は、LINE公式アカウントと、エースチャイルドさんが提供する「つながる連絡」を組み合わせた学校保護者連絡システムです。
先生や保護者はもちろん、教育委員会、PTA、部活動の連絡までがスムーズになり、コミュニケーションの効率化につながります。
特長をまとめると、
・9900万人が利用するLINEを使うため、保護者へのアプリ導入や説明が不要
・情報配信や欠席連絡、資料提出や日程調整、決済集金まで、幅広く網羅
・高い既読率と返信率で、先生の業務負担を大きく軽減
といった点ですね。
基本機能は無料で、現在、野田市さまに利用いただいているベーシックプランも無償トライアルを実施中です。

LINEスクール 連絡帳とは? 機能や特長から導入方法まで
――すでに他の連絡アプリ(サービス)がある中で、野田市がLINEスクール 連絡帳を選んだ決め手は何だったのでしょうか?
まず、現場で課題が大きく、校長会からも「負担を減らしたい」「一括で導入できるサービスを」と強い要望があり、私は複数のサービスを検討していました。
その上で着目したのは、教育委員会から保護者に直接送れる点と、保護者に説明がしやすい点です。LINEはすでに多くの方の生活に根付いているプラットフォームですから、「新しいアプリを入れてください」と言わずに済むのは大きなメリットでした。
また、予算編成が終わっていたため、コストをかけられませんでした。他サービスの有料版と比べても、無料トライアルで試せる機能が充実したLINEスクール 連絡帳の方がメリットは大きいと判断しました。
結果的に、ニュースを見てリリースを知ってから1、2週間ほどで導入を決めました。

――非常にスピーディーですね。役場や教育の世界では時間がかかりそうなイメージですが。
なんとしても、迅速に課題を解決したいという思いで動きました。
ただ、4月の新学期から全33校で一斉に始めるのは大変で、準備は苦労しました。LINEヤフーさんやエースチャイルドさんに、オンライン研修会を開いていただくなど、迅速で丁寧なサポートのおかげで、スムーズにスタートできたと思います。
――導入にあたって、不安や反対の声はなかったのでしょうか?
当初は先生から「保護者とLINEで直接つながるのでは?」といった誤解もありました。ですが、学校側は専用の管理画面を使う仕組みであること、また国内データセンターで安全に運用していることを丁寧に説明し、理解を得られました。ここは大きなポイントでしたね。

――LINEスクール 連絡帳の強みとして、他にどんな点がありますか?
ほとんど、木之下さんにお話していただきましたが、初期登録がとにかく簡単です。他のサービスですとアプリのダウンロードや登録が必要ですが、いつも使っているLINEなら1分程度で完了します。
また、即時性と反応の高さも特長で、配信をその日のうちに約8割の人に読んでくれるというデータが出ています(※3)。保護者の見落としを防ぎ、返信も早いので、追いかけ電話などが不要というわけです。
※3:LINE公式アカウントに関するエンドユーザー向け調査2021年7月21日(水)~2021年7月22日(木)実施n=2,060
現場から見ると、もう一点、大事なポイントがあります。
起きてほしくはないですが、万が一の災害時にも他のサービスと比べて「安否確認をしやすいだろう」と感じました。
学校側を説明した際も、この点は誰もが納得する部分でしたね。

野田市教育委員会での活用事例
――実際に使い始めて、どのような変化がありましたか?
まず、遅刻や欠席などの連絡がLINEでできるようになり、朝の電話対応が大幅に減りました。
さらに、教育委員会から保護者に直接文書を送れるようになったことも効果的でした。市役所のさまざまな部署から依頼があり、4月から8月までに配信した数は160〜170通にのぼります。送りやすくなっただけでなく、「しっかり届いている」、「読まれている」という手応えがあります。
――すごい数ですね。その効果を実感した具体的な場面はありましたか? また、工夫があれば教えてください。
はい。毎年、夏休みに子ども向けのイベントを実施しているのですが、今年はその告知後、応募が殺到して、あっという間に枠が埋まりました。昨年と比べたら数十倍のスピードですかね。その既読率と、反応の速さに驚きました。
しっかり読んでもらえているからこそ、保護者の負担を減らせるように、私たち教育委員会からの配信は、基本的に平日のお昼12時に行うルールにしています。

――現場や保護者からの声はいかがでしょうか。
学年や学級、部活動、特定の個人など、必要な情報を必要な人に簡単に送信できますから、先生たちからは「見やすい」「使いやすい」という声が多いです。
中学校では部活動連絡に活用し、アンケート機能で大会の参加希望を集めるなどの工夫もしています。
保護者からは、「設定が簡単で助かる」「大事な情報を確実に受け取れる安心感がある」と好評です。

今後のさらなる教育DX推進に向けて
――木之下さんが今後、期待する機能はありますか?
野田市は外国籍の方の転入がかなり、多い地域なので、まずは多言語対応をぜひ強化してほしいですね。
それから集金機能のさらなる充実を期待しています。現状、私たちはまだ使っていないため、子どもたちが現金を学校に持ってくるケースがあります。この慣習をなくせれば、子どもたちはもちろん、先生にも保護者にも大きなメリットになります。
――それでは、木之下さんが教育DXを進めて実現したいことを教えてください。
子どもたちに健康で、安心して学生生活を送ってほしいですね。
LINEスクール 連絡帳は有効に活用できると実感していますし、先生の働き方改革にもつながっています。
先生は、任期や異動も多いため、どこの学校でも同じシステムを活用できる点は大きなメリットです。先生が余計な負担やストレスを抱えず、子どもたちにしっかり向き合える環境を整えていきたいですね。
そして、野田市のキャッチコピーは、「元気で明るい家庭を築ける野田市」なんです。教育DXもその実現につなげていきたいですね。
――黒田さん、LINEヤフーが教育の課題に取り組む意義はなんでしょうか?
社会をつくるのは人であり、その人が課題を解決する力を育むのが教育です。AIの時代になっても、この役割は変わりません。だからこそ教育は、私たちが中長期で責任を持って取り組むべき重要な領域だと考えています。
「教育が変われば、社会は変わる」。その言葉は私たちの原点であり、ゴールでもあります。子どもたちや先生が安心して学び、働ける環境を整え、社会をより良くしていく。LINEヤフーとして、その基盤づくりに挑戦していきたいと思います。

取材日:2025年8月26日
文:LINEヤフーストーリー編集部 撮影:芹澤 明彦
※本記事の内容は取材日時点のものです
- LINEヤフーストーリーについて
- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。
コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。