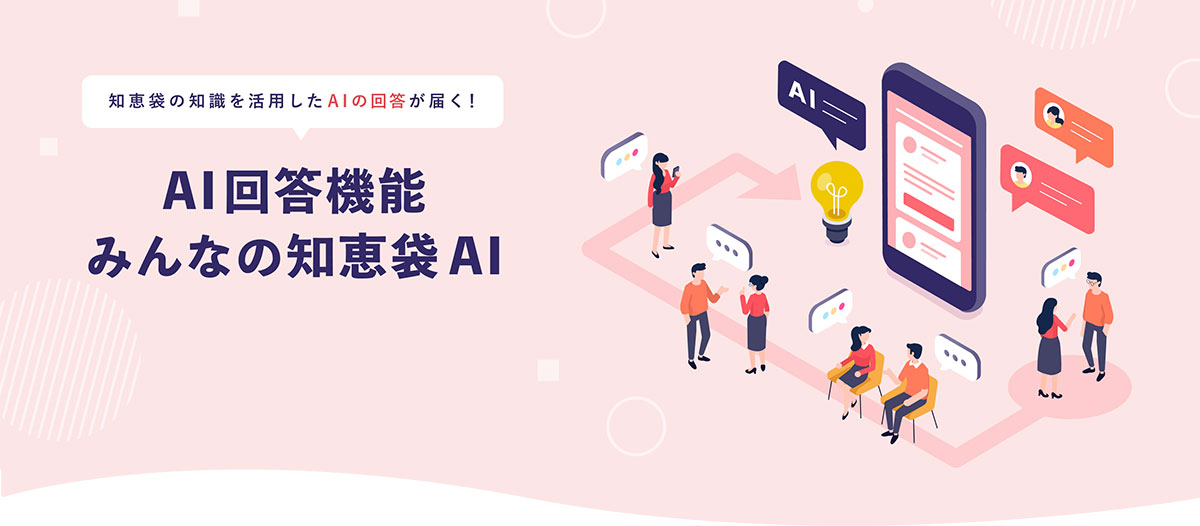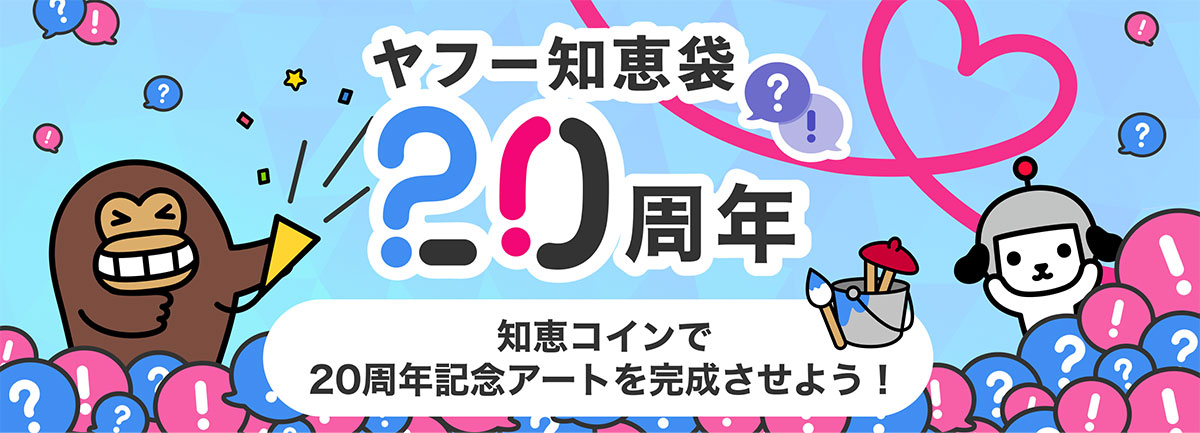知恵袋は、疑問に思うことを質問したり、回答したりして、ユーザー同士が知恵や知識を教え、分かち合うサービスとして20年前に誕生しました。デバイスや機能面では、PCウェブから、スマホウェブ、アプリ、生成AIと、その時代の最新技術に対応してきましたが、Q&Aサービスというサービスの軸は20年前から変わっていません。
今年9月には、みんなの知恵袋(※)をリリースしました。これは、過去20年の知恵袋データの中から似たような質問に対するベストアンサーを集め、それらを参考に生成AIが回答を生成するというものです。ただ生成AIを使うのではなく、ユーザーのみなさんが過去に回答してくれた知恵とテクノロジーをかけ合わせることにこだわりました。