LINE AIアシスタントは何ができるの? 担当者に聞く、友だちと会話する感覚での生成 AI 活用術
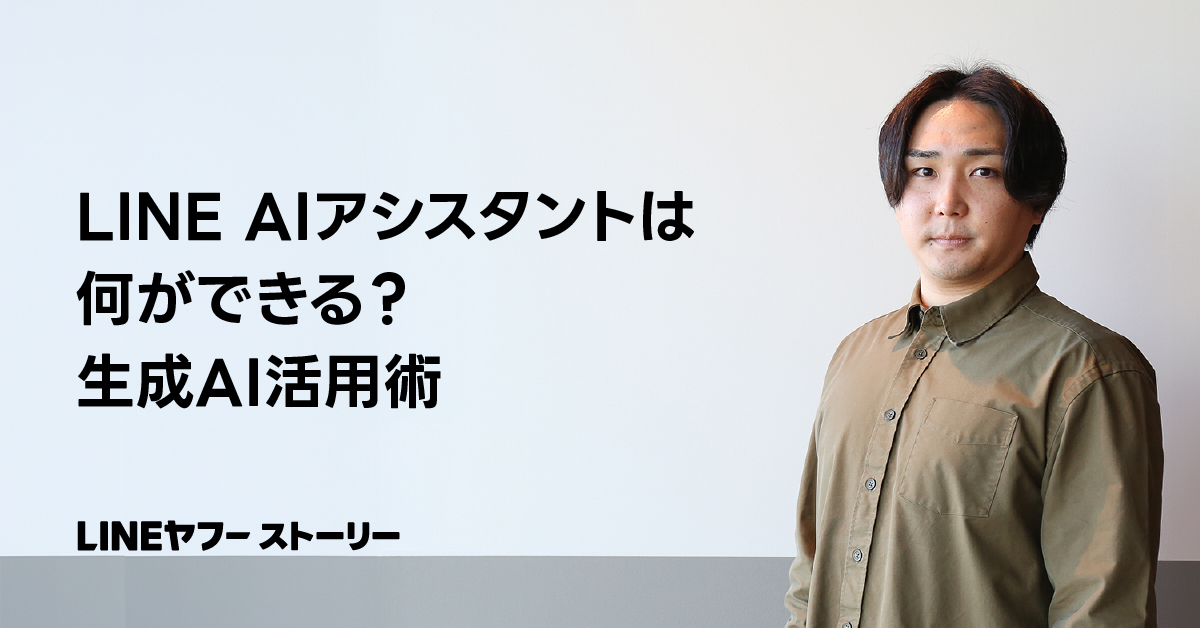
LINEヤフーでは、画期的なテクノロジーである生成AIの活用に取り組んでおり、OpenAI社とも利用契約をいち早く締結。生成AIを利用した新しいサービス、機能が続々と誕生しています。
2024年2月21日には、LINEアプリ内の新サービス LINE AIアシスタントが登場しました。友だちとトークする感覚で生成AIを活用でき、AIによる情報検索や画像の翻訳・解析などもできます。どんな狙いがあって企画したのか。一体、何ができるのか。企画を担当した鈴木に話を聞きました。

鈴木康介(すずきこうすけ)
2020年LINEに企画職で新卒入社。プロダクトマネージャーとしてLINEレシートの企画・開発などに関わった後、現在はLINE AIアシスタントの企画・開発を行う。趣味はポーカーで、生成AIにハンド(手札)の解析をしてもらうことも。
ユーザーの日常生活で生じる疑問や問題を解決するサービス
――このサービスでどんなことができるのか、内容を教えてください
LINE AI アシスタントは簡単に言うと、ユーザーが日常の生活で抱えるちょっとした疑問、問題を解決するサービスです。LINEアプリを利用していて、たとえば、友だちとトークしている中でふとした疑問がわいたり、知らない単語が出てきたときに、気軽にAIに質問・相談できます。
AIの回答からネット検索ができるほか、ファイルの翻訳・要約機能、料理の解析などもしてもらえます。また、画像の翻訳機能もあるので、海外旅行に行ってお店に入り、英語のメニューがわからないとき、写真をLINEアプリで送るだけですぐに翻訳してもらえます。
今後も機能アップデートを続けて、幅広いシチュエーションで、ユーザーに問題が生じた際、素早く解決できればと思っています。
生成AIは近年、世界的に話題になっていますが、聞いたことはあってもまだ使ったことがない方は多いと思います。また、すでにいろんな企業が関連サービスを立ち上げていますので、自分に合うものを探すのが難しいかもしれません。新規で会員登録をするのが面倒な方もいるでしょう。
その点、LINE AIアシスタントでは、いつも使っているLINEアプリから、そのまますぐに生成AIが試せますから、初めての方もこのサービスをきっかけに生成AIに触れていただけたらと思います。
専用ページからLINE公式アカウントを友だち追加することで簡単にご利用いただけます。一日5通までAIからの返信を無料で受け取ることができる無料プランと、月額990円(税込)で、全ての機能が使い放題の有料プランがあります。
有料プランでは、より高度な機能を試していただけますし、初回登録時に有料プランを3日間無料でお試しいただける体験期間に加え、2024年3月20日まで月額が500円(税込み)になるキャンペーンも展開しています。実際に試してみて、「こんなことができるのだったら、課金してみよう」という形で有料プランを使ってもらえたら嬉しいですね。

LINE AIアシスタントの使い方(ホームタブの「サービス」から開いて、簡単に追加・利用できる)
――料理の解析は具体的にどんなことができるのですか? また、ファイルの翻訳・要約機能はどんな利用シーンを想定していますか?
まず、料理解析では、料理画像を送ると生成AIが解析してくれて、カロリーや栄養素を表示してくれます。また、そこから調理法も教えてもらえます。私もいろいろ試してみましたが、たとえば、沖縄料理の集合写真を送信したところ、ソーキそば、ラフテー、海ぶどうなど、それぞれをピンポイントで高い精度で識別して、カロリー計算をしてくれました。健康を意識して、カロリーを気にされている方など多いでしょうから、重宝するのではないかと思います。
また、ファイルの翻訳・要約機能はビジネスパーソンはもちろん、学生さん、研究者の方などに、レポート作成、論文を読むときのサポートに使っていただくケースを想定しています。
これらをLINEアプリ内で簡単にできてしまうのがわれわれの強みです。いつもLINEアプリを活用している方なら、スムーズに気軽に、ハードルなく行っていただけるのではないでしょうか。

料理の解析シーン(次にやるべきことがわかりやすいUI)
高度なAI機能を多くのユーザーに届けるために工夫したUIやUX
――どういう狙いで企画したのですか?
全社的に生成AI活用に取り組んでいますが、LINEアプリのトーク機能を担当しているコミュニケーションカンパニーでも、「トークと親和性の高い生成AIを活用しない手はない」ということで、プロジェクト自体は1年ほど前に立ち上がりました。
しかし、なんでもできるからこそ、どういうプロダクトをつくるか、ユーザーにどんな価値を提供していくかは難しく、試行錯誤したところなんです。
LINEアプリはとても幅広い世代の方に使っていただいているサービスです。高度なAI機能をより多くのユーザーに使っていただくためにはどうすれば良いか、という視点で企画しました。そのため、ニーズが高そうなシンプルな機能やアプローチを考え、UIやUXにもこだわりました。
ライフプラットフォーマーを目指しているLINEヤフーとして、ユーザーの暮らしが便利になるような価値を届けたいですね。
――サービスを進めるうえで、大事にしたポイントはどこですか?
企画の視点ですと、生成AIという高度な機能を、まだ慣れ親しんだことがない方に対して、どうやってハードルを下げて、スムーズに使ってもらえるかが一番難しく、かつ大事なポイントでした。直感的に使ってもらえるような工夫をしていて、たとえば、生成AIの回答に対して、次のアクションをタップするだけで指定できる機能があるのですが、ユーザーが悩まずに自然とやるべきことがわかるような仕組みになっています。
それに加えて、日常的な利用ケースを広げるところも意識しました。画像の翻訳機能、ファイルの翻訳・要約機能の提供、料理画像の解析もそうですが、日常的な利用シーンを広げるところも一つひとつ工夫しています。
現在の生成AIの主な用途としては、サービス開発の補助だったりアイデア出しのサポートだったり、技術・ビジネス寄りの用途がメインです。それをいかに日常的な利用ケースに広げられるかというのは、大きなポイントだと思っています。
ただ、現状LINE AIアシスタントで提供できているのはまだまだ一握りの利用ケースに留まっているので、今後、グループ内のサービスとの連携も含めて拡大していきたいですね。
――企画を進めるうえで、苦労したことはありますか?
このプロジェクトはメンバーも多国籍で、外国の企業とAPIの利用契約を結ぶなど、グローバルな開発体制でした。ユーザーに安心して使っていただくためのセキュリティなど守りの部分まで、社内外、多くの関係者とのコミュニケーションは慎重に進めました。
英文でのメールでのやりとりには、生成AIを活用して効率化を図りましたし、日本語のエラー画面を英語に翻訳して共有して解決するなど、LINE AIアシスタントの機能も活用しています。

グループ内の各サービスと連携して、もっと便利な世の中に
――入社間もない時期から重要な役割を担っていますが、イメージとのギャップはありませんでしたか?
実は、私はAIに関しては学生時代から本当に興味があり、新卒でLINEを受けた面接時、「10年後、20年後どうしたいか」と言った質問を投げかけられたときに、「最終的にはAIがどんどん発達していってパーソナルAIになるのではないか」、「新しいサービスが出てくると思うので、それを自分でつくりたい」という思いを話していました。
当時は感覚的に、「あと5年、10年ぐらい先かな」と思っていたら、2022年11月に、ChatGPTが公開されて以降、状況が一気に進み、「このタイミングを逃すのはもったいない」と、現在の部署に自分から異動希望を出しました。
やる気さえあれば本当にいろんなチャレンジをさせてくれて、大きいプロジェクトのリードなど、責任あるポジションもどんどん任せてもらえる恵まれた環境だと感じています。
――LINEアプリは幅広いユーザーを抱えていますが、今後、AIをどのように活用していきたいですか?
私自身も初めて生成AIに触れたときに、ただテキストを送るだけで、「こんなに自然で、ほぼ人間と遜色ないぐらいのことを、なんでも返してくれる!」という驚きや感動を強く感じました。まさに、LINEヤフーが大切にしているWOWや!ですね。ぜひそれをたくさんの方々に感じてほしいです。
日本人の誰もが生成AIを使いこなせるようになったら、生産性の向上につながるでしょう。ですから、ユーザーの生活を想像しながら、もっともっと日常の体験にも落とし込んで、便利な世の中にできるといいなと思っています。
LINEヤフーのミッションは、「『WOW』なライフプラットフォームを創り、日常に『!』を届ける」ことです。文章の校正やメッセージの要約などトーク観点でも生成AIを活用してできることはまだまだたくさんありますし、今後もトークやコミュニケーションに関わるユーザーの課題をどんどん解決していきたいです。
また、生成AIのアウトプットの品質向上という観点だと、Yahoo!ショッピングやYahoo!マップをはじめ、LINEヤフーのグループ企業が持つたくさんのサービスは大きな優位性だと思います。LINE AIアシスタントがハブになって、グループ内の各サービスへの橋渡しとなり、さまざまな利用ケースで質の高い独自コンテンツを提供していけるようになるのが理想です。
取材日:2024年2月14日
※本記事の内容は取材日時点のものです

- LINEヤフーストーリーについて
- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。
コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、「WOW」や「!」を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。


