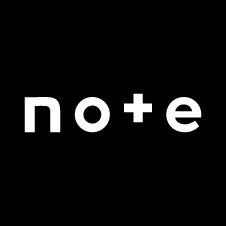鈴木 康介
社会的インパクトをチームで
生み出す。LINE×AIの
可能性を信じるプロダクトマ
ネージャーの展望
社会的インパクトをチームで生み出す。
LINE×AIの可能性を信じるプロダクトマネージャーの展望
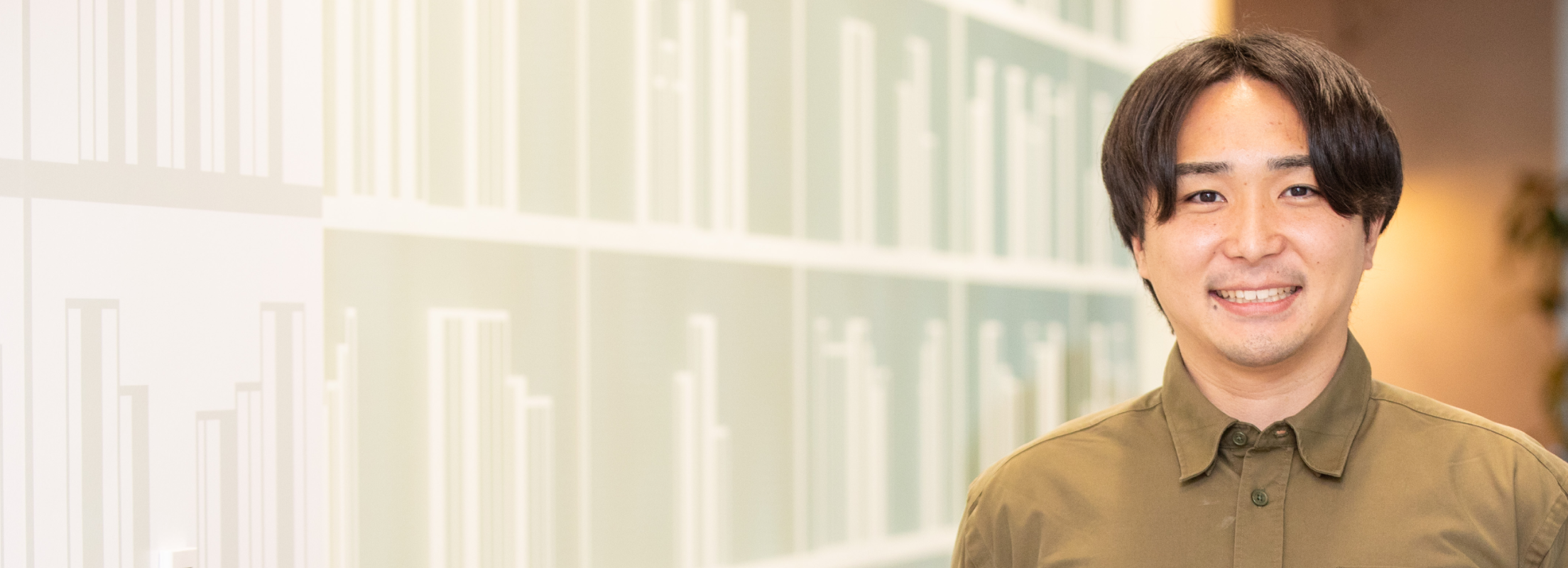
鈴木 康介(すずき こうすけ)2020年入社
LINE(現LINEヤフー)に企画職として新卒入社後、「LINEレシート」のプロダクトマネージャーを経て、2023年からは「LINE AIアシスタント」、生成AIデータ処理プラットフォームのプロダクトマネジメントに従事。
※本記事は2024年9月に取材したものです。サービス名称や所属は取材当時の内容です。
自己紹介をお願いします。
2020年に企画職として新卒入社した鈴木康介です。「LINEレシート」のプロダクトマネージャーを経て、2023年5月より「LINE AIアシスタント」の企画開発を担当しています。
子どものころから、自分で考えたものを形にして誰かに届けることに対して強い想いを持っていました。学生時代は理系で、経営工学を専攻していました。経営工学の講義でプログラミングや情報工学の演習があり、その流れでアプリやWebサービスに興味を持つようになったんです。
そこから自分でもアプリやサービスをつくってみたいと思い、友人とアプリをつくったり、ビジネスコンテストに参加したりしていました。つくりたいものを実際に形にするために、講義で学ぶだけではなく、プログラミングをもっと勉強したいと思うようになりました。その後、就職活動では旧LINEの選考を受けることに決めたのですが、当時はエンジニア職と企画職で決めかねており、2職種の選考を並行して受けていました。プロダクト開発について学び、理解を深めていくうちに、自分は開発そのものよりも「どんなプロダクトをつくって、何をユーザーに届けるのか」を考えるプロセスにおもしろみを感じていることに気づいたんです。企画職はより自分のやりたいことを実現できる職種だと思い挑戦を決めました。 やりたいことは当時もいまも変わらず「ユーザーの課題をいかに解決するか」です。

入社後は2年ほど「LINEレシート」(2024年6月にサービス終了)のプロダクトマネージャーを務め、2023年5月に自ら希望を出して「LINE AIアシスタント」に異動しました。就職活動をしていた頃からAIには大きな可能性を感じていて、「今後はAIがやりたいことを代わりにやってくれたり、アシスタントとしてサポートしてくれたりする世界が来るはずですし、その世界をつくっていきたい」と語っていたほどです。当時は5年、10年先だと思っていましたが、2022年末のChatGPTの登場でパラダイムシフトが起きましたよね。同時に、「LINE」は「チャットによるAIとの対話」という領域と非常に親和性が高い。「この業界に入るときに思い描いていた未来を実現できるチャンスが巡って来たのだから、今やらなければ…!」と当時の上長に直談判しました。僕の熱意を受け止めて、最後には「それなら行ってこい」と快く送り出してくれた上長には今でも感謝しています。
現在担当している主な業務内容や具体的な流れについて教えてください。
企画開発を行った「LINE AIアシスタント」が無事リリースされ、現在は「LINE」のトークにどうAIを活用していくかの企画検討を行っています。「LINE AIアシスタント」は、簡単にAIを使える環境をスピーディに提供することを目指したもののため、「LINE公式アカウント」をベースとした対話形式の汎用的なAIの形をとっています。今後はもう一歩踏み込んで、トークそのものの中にAIを機能として取り込んでいくためにさまざまな検証を行っているところです。
また、安全性を高める動きも進めています。「LINE」のトーク内容は、通信の秘密として保護されていることを前提に、慎重に取り扱うことが必要です。ユーザーが安心してAIを活用できるようなデータ処理プラットフォームを構築するための、バックエンドの環境づくりにも取り組んでいます。
1日のスケジュール例
- 10:00
- 出社、勤務開始
- 1日のスケジュールとSlack・メールの確認
- 10:30
- 会議の準備や資料作成
- 13:00
- ランチ
- 14:00
- プロジェクト全体の定例会議
- 15:00
- 部署の定例会議
- 16:00
- プロジェクトメンバーと進行案件の相談・すり合わせ
- 17:00
- 作業時間
- 仕様や会議で確定したことの整理
- 20:30
- 勤務終了
- 勤務終了後はジムに行くことが多いです。
会議が少ないときは機能について考えたり、スペックをまとめたりしています。最近は夜にジムに行くようにしていて、きちん身体を動かしてリフレッシュすることも大切にしています。
仕事を進めるうえで意識していることはなんですか。

LINEヤフーのカルチャーともいえる部分ですが、やはり「本質的にユーザーが求めているものは何か」「ユーザーが抱えている課題は何か」を突き詰めて考えることです。ユーザーインタビューなども定期的に行い、どのようなAIの使い方をしているのか、何か困っていることはないかなど、さまざまな声をお聞きしています。
実際にユーザーに聞いてみると、「子どもに『なんで空は青いの?』と聞かれ、回答に困ったのでAIに聞きました」など、すぐに調べても簡単に答えが見つからないものに対してはAIに聞いた方がはやいようなケースが見られました。このように、想像していたものとは異なる使い方や意外な答えに驚くことも多いですね。そうやってインサイトを得るからこそ新しい使い方を提案できますし、提案を行うからこそ、ユーザーにとっての可能性を広げられるのではないかと考えています。
AIの領域ではまだ誰も正解がわからない状況ですが、それでも結局、ユーザーの課題を解決できるものやユーザーが価値を感じるものを提供できなければ、プロダクトが使われることはありません。どんな領域であっても、「ユーザーに何を提供できるのか」を考え続けることが大切なのではないでしょうか。
入社してから印象に残っている仕事やプロジェクトについて教えてください。

「LINEレシート」時代に、価格比較ができる機能の立ち上げに取り組んでいたときのことです。この機能は、レシートの写真を撮るとそこに記載されている商品や価格が認識され、近隣のスーパーやコンビニの価格データと比較することができるというもの。バックエンドの仕組みが非常に複雑で、精度の担保にも課題があったため、立ち上げからリリースまで1年近くを要しました。
この機能の開発が難しかったのは、「そもそも本当にできるの?」というところからのスタートだったことです。開発チームに相談しても、はじめは「どうやって正確に商品を認識できるのか」「今の技術では実現が難しいのでは」という反応でした。それでも、上長と二人三脚でデータをつなげるスキームを検討し、自ら解決策を考えて提案することで乗り越えられました。プロダクトマネージャーは、思い描いたプロダクトや機能を実現するために、できることはすべてやるのが仕事です。課題を特定し、どうすればその課題をクリアできるか自ら考え、行動することが大切だと実感しました。
無事リリースに漕ぎつけ、使ってくれたユーザーの「めちゃくちゃ便利!」「こういうのが欲しかった!」という反応を見たときは、本当にやってよかったなと思いました。
このときの経験は今も生きています。「AIなら何でもできる」と思われがちですが、実際はデータをどう蓄積していくのか、高い精度を担保するためにはどうすればいいのかなど、考えなければいけないことが山ほどあります。さまざまな制約がある中でどう形にしていくのか、どう工夫すればいいのかなど、常に考えるようにしています。
自分の成長を感じるポイントはどんなところですか。

入社1年目から「LINEレシート」のプロダクトマネージャーという大きな仕事を任せてもらい、その役割を通じて徐々に成長してきた感覚があります。もちろん自分ひとりではなく、当時の上長などの手厚いサポートがあってのことなので、本当に感謝しています。成長には運やタイミングの要素が大きかったと思いますが、自分自身としても、チャンスが来たときに「鈴木さんになら任せられる」と思ってもらえるだけの信頼を得られるように、目の前の仕事に常に誠実に取り組んできました。
ただ、ほかのメンバーを頼ることが苦手で、自分ひとりで抱え込みすぎてしまうことがありました。過去にはメンバーと対立してしまったり、コミュニケーションミスがあってうまく意思疎通がとれなかったりしたことも。KPIを達成しようと数字ばかり追いかけて頭でっかちになってしまい、メンバーとのコミュニケーションをないがしろにしてしまったんです。今振り返ると、一歩引いた視点から状況を俯瞰し、相手の考えや意見を汲みながら柔軟なコミュニケーションが取れていればうまくいったのでは…と思っています。
それでも、そういった失敗の経験や反省からさまざまなことを学びました。やはり自分ひとりでできることには限界がありますし、メンバーを巻き込んで一緒に進めていくことができれば、チームとしての成果を最大化できるはず。今後は、「チームとしてどう動いていくか」の視点をより一層大切にしていきたいです。
入社して良かったと感じることはなんですか。
LINEヤフーのバリューのひとつでもある「ユーザーファースト」の考え方、ユーザーが求めているものを突き詰めて考える姿勢は、本当に素晴らしいものです。サービスやプロダクトをつくるうえでもっとも大切なことですし、そのマインドがカルチャーとして隅々まで行き渡っているのを感じます。会議などでも「これで本当にユーザーの課題は解決できるのか?」など、常にユーザーを中心として議論が進むのが良いところです。
僕はサービスやプロダクトをつくりたくて入社したわけですが、まさにやりたかったことができていますし、そのコアとなる考え方を吸収できていると感じています。身につけてきたユーザーファーストの考え方は、今後別の事業やプロダクトをつくることになっても変わることはないでしょう。
若いうちからこれだけのことを任せてもらえる裁量という点でも、想像以上でした。入社1年目に「LINEレシート」を任せると言われたときは本当にびっくりして、「僕でいいんですか?」と聞き返してしまったほどです(笑)。どのプロダクトもユーザーの規模が大きく企画の範囲も広いので、本当にやりがいのある環境だと思います。
今後の目標を教えてください。

現在日本のAI使用率はまだ低く、9%程度と言われています(総務省発表/個人利用の割合)。一方で「ぜひ利用してみたい」「条件によっては利用を検討する」と答えた人の合計は7割を越えており、実際の使用率と大きく乖離があります。「LINE」は多くの人々が使い慣れているアプリのため、AIの価値を届けるのにこれ以上ないプロダクトではないでしょうか。そのポテンシャルをしっかり生かし、社会的なインパクトを実現していきたいです。
またユーザーが求めるものを提供することに加え、最新の技術やソリューションを組み合わせて、より良い機能やアウトプットを提案していきたいです。実際、社内に優れたソリューションやAI機能があるのに、それをプロダクトに生かせていない例が多々あります。そういった社内の技術にもアンテナを張り、ユーザーの課題と掛け合わせてプロダクトの機能に落とし込んでいこうと取り組みはじめているので、その動きを推し進めていきたいです。
中長期の目標としては、「LINE AIアシスタント」をもっと発展させ、より広い範囲でさまざまなアウトプットを生成できるようにしていきたいと考えています。たとえば観光の領域であれば、旅行のスケジュール調整を自動化し、観光プランやレストランを提案するところまでやっていきたいですね。そのためには、どういうデータをどうやってつなげたらいいのか、そこから質の高いアウトプットを得るにはどのような仕組みが必要なのかなど、全社で取り組んでいかなければいけません。簡単なことではありませんが、その先により良いユーザー体験が待っていると思うので、この大きな挑戦に取り組んでいきたいです。
僕個人としては、さきほど話した「チームとして成果を出す」ことに挑戦していきたいです。AIを日本に普及させることは、自分ひとりだけでは絶対に実現できません。企画のメンバーだけでなくデザイン、開発なども巻き込んで、チームで一丸となって進めていけるよう、今後もプロジェクトをリードしていきたいです。
これからのLINEヤフーに期待していることを教えてください。
幅広い領域でサービスやプロダクトの展開を行い、それぞれに質の高いデータを保有していることが、LINEヤフーグループ全体の強みだと考えています。ECなら「Yahoo!ショッピング」、旅行なら「Yahoo!トラベル」、そして「PayPay」など金融サービスもあります。それらをどうつなげてAIに落とし込んでいくかが非常に重要ですし、あらゆるデータをうまく組み合わせることができれば、賢いAIコンシェルジュなどをつくることができるのではないかと期待しています。
最後にメッセージをお願いします。
これだけ広い範囲をカバーする質の高いデータを保有している組織は、LINEヤフー以外にないのではないでしょうか。その強みを生かしてプロダクトをつくっていくことに、本当にやりがいを感じています。また、「LINE」も「Yahoo! JAPAN」も多くのユーザーがいるので、プロダクトをつくって終わりではなく、ユーザーに届けるところまでカバーできるのも魅力です。自分の考えたサービスやプロダクトをみんなでつくり、多くのユーザーに届け、新しい価値を生み出していきたいと考えている方に、是非興味を持ってもらえたら嬉しいです。