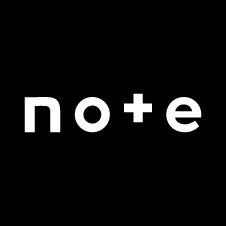黒木 隆史
情報技術のチカラで日常生活
をもっと楽しく変えていける
。
情報技術のチカラで日常生活をもっと楽しく変えていける。
黒木 隆史(くろき たかふみ)2017年入社
ヤフーに新卒入社し「Yahoo!ショッピング」にアプリケーション開発エンジニアとして携わる。
※この記事は、2022年に取材・掲載したものを一部修正して再掲載しています。サービス名称や所属は取材当時の内容です。
現在担当している仕事について教えてください。

「Yahoo!ショッピング」におけるAndroidアプリと「お買い物クエスト」と呼ばれるゲームのバックエンドエンジニアリングを担当しています。ユーザーから届いた問い合わせ内容をもとに「サービスをどう改善していけば良いか」を考えながらアプリを改修しています。
友人や家族にアプリを使ってもらって意見を聞くこともありますし、ときにはSNSなどでエゴサーチをして改善すべき点をピックアップすることもあります。
特に「Yahoo!ショッピング」は昔からあるサービスのため、エンジニア目線で改善できる余地はまだまだあると考えています。たとえば、サービス速度を速くしてユーザーの使い勝手をアップさせるなど、技術的な改善に向けて、試行錯誤をする日々です。
仕事のやりがいや醍醐味、おもしろさは?
やはり自分が苦労して開発・実装した機能などを実際にユーザーに使ってもらったときは、一番やりがいを感じます。
たとえばPayPay祭などのキャンペーン時には、アクセス数が多くなることを見越して深夜の時間帯にテストを実施する必要があるため、一時的に勤務時間が昼夜逆転することもあります。また、24時間体制のサポートが必要な場合もあるので、オン・オフの切り替えをしづらい大変さもあります。
ただ、これもたくさんのユーザーにサービスを利用してもらっているヤフーならではの悩みかなと思っています。「Yahoo! JAPAN」はいろいろなサービスを包括するポータルサイトでもあります。あらゆるユーザーに活用してもらい、ITのチカラで日常のすべての生活をもっと楽しく変えていける点に魅力を感じたことが、入社するきっかけでもありました。
仕事をするうえで一番大切にしていることを教えてください。
自身が障がい者ということもあり、一番に気をつけていることは体調管理です。ヤフーでは、障がいを持った社員も快適に働けるための制度や設備が充実しています。また、入社前に自分と近しい障がいを持っている先輩社員の方にお話を聞く機会もあったため、その部分ではあまり心配はありませんでした。
制度だけではなく、社員が個々の能力を最大限発揮するために、困っていることがあったら何でも相談にのってくれる「グッドコンディション推進室」という部署もあります。

車椅子ユーザーは、ずっと座り続けていると体重で圧迫されて血流が悪くなったり滞ることで身体の一部がただれたり、傷ができる「褥瘡(じょくそう)」になりやすいため、毎日出社していたときにはずっと座って業務することが難しかったんです。そんなとき、グッドコンディション推進室に相談をしたら、すぐに会社の一角にベッドを置いてくれ、仕事をしやすい環境を整えてくれました。その後も定期的に連絡をくれたり、親身に相談にのってくれたりと常に気づかってもらえるので、とても安心して仕事を進められています。
1日のスケジュール例
- 10:00
- 勤務開始
- メールやSlackなどでその日の業務内容を確認します。
- 11:00
- チーム朝会
- 進捗や作業予定をチームみんなで共有します。
- 12:00
- ランチ
- デリバリーすることが多いです。ランチをとりながらオンラインで開催される社内の勉強会に参加することもあります。
- 13:00
- サービス定例
- 数字や今後のスケジュール、それぞれのタスクの進捗を確認。
- 13:30
- 開発とコードレビュー
- 必要に応じて調査タスクをこなしたり、問い合わせ対応をしたりすることも。Zoomやオンラインのホワイトボードなど、いろいろなデジタルツールを活用して、コミュニケーションを取りながら業務を進めています。
- 14:30
- 上長との1on1ミーティング
- 進捗や困っていることを共有。私生活の話もします。
- 15:00
- 開発とコードレビュー
- 19:00
- 勤務終了
よく利用している、あって助かる会社の制度は?

リモートワークになり、私と同じ車椅子で生活している社員も含め通勤がなくなったことが大きな変化だと思っています。身体への負担もかなり軽減されました。突発的な体調不良になることもありうるので、リモートワークでは安心して仕事に集中できています。いろいろな心配ごとがなく、常にリラックスした状態で業務に取りかかれています。また、障がいにともなう通院などで年間6日間取得できる「ノーマライゼーション休暇」も活用しています。丸一日だけではなく、半休でも使えるので、午前中に通院し午後から通常勤務に戻ることもできます。
今後の目標を教えてください。
入社してからずっと「Yahoo!ショッピング」に携わっていますが、私が触れているのはまだそのごく一部。もっと勉強をして、理解を深めて「Yahoo!ショッピング」の発展に貢献していきたいです。
また、将来的にはアプリエンジニアとしてだけではなく、Webのフロントエンジニアやバックエンドエンジニアとしても活躍をしていきたいと思っています。ソフトウェアの開発や使用する言語についても、Webとアプリでは異なってくるため、まだまだ勉強をしてスキルを上げていかないといけないため、頑張っていきたいです。
最後にメッセージを。
障がいが何かの妨げになることはなく、むしろ強みとして生かせると思っています。障がい者は、障がい者のなかにいるとそれが普通になってしまうけれど、健常者と一緒にいると個性に変わっていくと私は思います。
たとえば、色覚障がいを持っている方であれば、「このアプリの色使いだと視覚障がいを持つ人にとって見にくい」という貴重な意見を伝えることができます。
特にLINEヤフーのサービスを使っているユーザーは膨大で、そのなかにはもちろん、障がいを持つ方も多くいらっしゃると思います。
そうしたユーザーの声を代弁できることは、それだけですごい存在なのではと私は思います。
障がいがあっても、あなたの力を発揮できる仕事がありますので、ぜひチャレンジしてください。