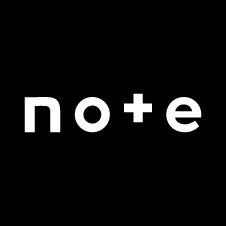佐藤 彰真
幅広い専門性を持ったデザイ
ナーを目指して、ユーザーフ
ァーストのプロダクトを追求
する。
幅広い専門性を持ったデザイナーを目指して、
ユーザーファーストのプロダクトを追求する。

佐藤 彰真(さとう しょうま)2020年入社
新卒でデザイナーとして入社し、「LINE証券」「LINE FX」「LINE CFD」など金融系サービスのUIデザインを担当するチームでプロダクトデザイナーとして勤務。
※この記事は、2022年に取材・掲載したものを一部修正して再掲載しています。サービス名称や所属は取材当時の内容です。
自己紹介をお願いします。
佐藤彰真です。2020年に新卒でLINEへ入社しました。主に日本で展開しているサービスのデザイン等を統括するデザイン組織に所属し、「LINE証券」「LINE FX」「LINE CFD」など金融系サービスのUIデザインを担当するチームでプロダクトデザイナーとして働いています。
学生時代は情報系の工学部だったのですが、カリキュラムのなかで情報デザインに触れたのをきっかけに夢中になり、インターンシップやスタートアップ企業で働きながらデザインを学びました。就職活動ではIT系の事業会社を志望していたので、LINEは自然と選択肢に入っていたのですが、デザイナー採用枠のうち、BX領域とUI領域を分けて募集していた点に魅力を感じ、入社を決めました。プロダクトデザイナーとしての専門性を追求したい私の希望にマッチする環境、業務体制が整っていると考えたからです。実際、LINEは非常に分業体制がしっかりしていてデザイナー職のなかでも専門領域がはっきり分かれており、やりたかったUIデザインに専念できています。

これまでどのような仕事を担当してきましたか。
研修は約1ヶ月と短く、入社してすぐに実際の業務に携わることができました。最初は先輩デザイナーとツーマンセルで案件を担当し、社内のワークフローや他部署とのコミュニケーションの取り方等を学びました。
業務内容もラベル変更のような小さな作業から始めて、徐々に既存サービスの機能改善といった大きめの案件に移行していきました。その過程で既存サービスの設計理念や細かなトーン&マナー、デザインシステムなどの具体的なことをインプットし、LINEのデザイン業務そのものへの理解を深めていきました。
初めての大きな案件は、1年目に先輩と一緒に担当した「LINE FX Pro」の新規UIデザインです。スマホアプリとして展開している「LINE FX」のPC版を新たに開発するプロジェクトでした。この案件ではまず事業部側からサービスの仕様や要件、各画面のワイヤーフレームなどを共有してもらい、それを土台にしてUIデザインを進めていきました。サービスのスタイルやメインの画面は先輩が作成し、私は設定画面などの細かな画面を担当しましたが、入社してこんなにも早く新規サービスのデザインを担当できるのかと、当時は驚きつつワクワクしたことを覚えています。
先輩やマネージャーからのフィードバックもかなりの頻度でもらえ、それにともなって自分のデザインの判断が速くなっていく実感がありました。この案件を含めた、日々の業務における1000本ノックのようなやりとりが、デザイナーとしての力量を底上げしてくれたと思っています。
あっという間に2年目になり、簡単な修正案件などは一人でもこなせるようになっていきました。加えて先輩の担当する案件にパターン出しとして参加することも増え、その度に先輩のアウトプットと自分のものを見比べ、視覚的にも魅力的な画面作りを体感しながら業務に打ち込んでいきました。
3年目の現在は、他部署とのやりとりやデザインの作成など、プロジェクトのスタートからクローズまでひとりで案件を担当することが増えてきました。もちろんまだまだ勉強途中ですが、サービスのデザインそのものだけでなく、効率的なデータの運用方法やチームでの協業といった働き方の改善などにも目が向くようになり、プロダクトデザイナーとしてできることが増えていると感じています。

今までで一番印象に残っている、大変だったプロジェクトについて教えてください。
2022年の夏、初めて大きめのプロジェクトを一人で担当しました。それが、「LINE証券」に新機能を追加する改修です。大変だった点は、既存のユーザーフローの利便性を保ちつつ、そこに新機能をマージさせることでした。ユーザーの状態によって画面のバリエーションが複数あり、その整理にも頭を捻りましたが、ユーザーフローの整理が1番の山場でした。
複雑な操作を、その複雑さを感じないようにユーザーを誘導することの難しさを痛感しました。金融系のサービスは規制等で思ったようなデザインにできないことがしばしばあります。画面をシンプルにしたいのに、長々とした説明文を必ず記載しなくてはいけないケース等です。この案件も例に漏れず、画面内の情報を整理する点に時間を使いましたが、そういった制約をうまくクリアしていく楽しさもありました。
また、画面数が多い案件では、認識の共有をとても大切にしています。デザイナーと事業部、開発との認識がズレていると、画面数が多い分修正も大変です。逐一確認とすり合わせを行いながら、時に議論を交わしつつデザインを進めていきました。コンポーネントの配置やユーザーフローの意図など、なぜこのデザインなのかという説明の大切さはLINEで働くうえで学んだことです。この案件を含めた日々の業務を通じて、プロダクトデザイナーとしての自覚をより強く持てるようになったと思います。
自分の成長を感じるポイントはどんなところですか。
デザインの判断は入社時に比べて着実に速くなり、引き出しも増えたと思います。当初はボタンのサイズ一つ決めるのもかなり悩みましたが、今ではこれまでの経験をベースに「この画面にこの情報を載せるなら、フォントサイズはこれ、明度はこれくらい…」とスムーズかつある程度適切に判断できるようになり、業務スピードも上がりました。その分、いろいろなバリエーションを試すことができ、表現の幅を広げられたと感じています。
また、私は良いと思ったデザインをインターネットでリサーチし、収集することを日課にしているのですが、その甲斐もあってかさまざまなデザインパターンがインプットされ、リファレンスを調べる時間もぐっと短くなりました。これもUIデザインに専念できる環境があるからこそかもしれません。
ほかにも、インハウスのプロダクトデザイナーとしてさまざまなことに気を配れるようになりました。具体的には、データ運用の効率化やデザインシステムについての理解、他部署とのスムーズな連携方法などです。たとえばUIデザインではFigmaを使用していますが、画面を全てAuto Rayoutで作成してレスポンシブに対応したデザインにしたり、エンジニアが実装する際に理解しやすいドキュメントを作成したりするスキルは実際に働くなかで身についていきました。ツールの進化は日進月歩なので、新しい機能をいち早くキャッチアップして業務に活かすことも大切なスキルだと思っています。

入社して良かったと感じることはなんですか。
LINEには約100名のデザイナーが働いています。さまざまな領域のデザイナーの仕事を間近で見ながら視座を高められるのも魅力です。また、UIだけでなくグラフィックなどマルチなデザインスキルをデザイナーに求める企業も多いなかで、LINEはプロダクトデザインとBXデザインで領域が分かれているので、UIデザインにフォーカスして専門的にスキルを磨ける環境です。ひとつの専門性を突き詰められる環境を求めていたので、とても良かったと感じています。
事業会社なので納期死守のクライアントワークと違い、納得がいくまでデザインにこだわることができるのも良いところかもしれません。もちろんスケジュールは大事で、締め切りを無限に延ばせることはないのですが、目的は納品そのものではなく、良いプロダクトを出してすばらしいユーザー価値を提供すること。そのためにどうしても必要な時間であれば、しっかり会話をすることや関係構築をすることを前提に社内の理解は得やすいと思います。
「LINE」は19の言語で展開されるグローバルサービスです。日本語は言語の特性上どうしてもデザインが複雑になりがちですが、「LINE」では海外のサービスのようなすっきりとしたシンプルなデザインを目指しています。2021年11月には、カラー、アイコン、グラフィックなどを標準化したデザインシステム「LINE Design System」を設けたことによりグローバルで一貫性のあるデザインをつくりやすくなっていますが、ゼロから新たなサービスをつくるときは、リサーチからかなり時間をかけます。リファレンスはほぼ海外のものなので、日本にいながら世界の最新情報をキャッチアップでき、グローバルスタンダードなデザイン感覚を培えるのもLINEで働く大きなメリットだと思います。

今後の目標を教えてください。
最近では案件を一気通貫で担当できるようになってきたので、案件の規模や責任範囲を広げ、プロジェクトをリードしていきたいです。良いプロダクトをユーザーに届けるには、デザインに関することだけではなく、エンジニアリングやビジネス、コンプライアンス等の理解が必要だと思います。それらを横断的に理解しつつ、ユーザー視点に立ってデザインを提案できるようになりたいですね。
入社当初は、まず幹となるUIデザインを深く学び、そこから枝葉を広げるようにさまざまな領域の知識を身につけたいと考えていました。今でも気持ちは変わらず、その必要性をひしひしと感じています。LINEにはデザインひとつとっても、さまざまな専門性をもつ人達がいて、その活躍を間近で見つつ、自分の専門性を突き詰めていける環境があります。大勢のプロフェッショナルと協働しながら試行錯誤を重ね、ベストなデザインを模索していく道のりもまた、LINEで働く楽しさや醍醐味だと感じています。
最後にメッセージを。
LINEのデザイナーは本当にみんなデザインが好きで、業務時間外でもデザインのことを考えているような人たちばかりです。同じようにデザインが好きな人にとっては、このうえなく刺激的で楽しい環境ではないかと思います。そういう人たちが集まる場所で働いてみたい人にはおすすめですし、私自身もここで切磋琢磨して、まだまだ成長し続けていきたいです。