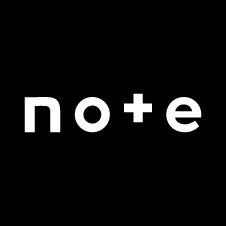加藤 ゆり
デザインガイドラインの価値
を信じて。サービスを支える
、一貫したユーザー体験にか
ける想い。
デザインガイドラインの価値を信じて。
サービスを支える、一貫したユーザー体験にかける想い。

加藤 ゆり(かとう ゆり)2020年入社
ポテンシャル採用でコーダーとしてヤフーに入社後、2021年に異動しデザイナーとして「PayPayフリマ」のUI/UXデザインに従事。
※本記事は2023年7月に取材したものです。サービス名称や所属は取材当時の内容です。
自己紹介をお願いします。
加藤ゆりです。もともとはまったく別の業界で事務の仕事をしていましたが、IT系の専門学校に通ってWebデザインを学び、2020年にポテンシャル採用でヤフーに入社しました。
就職活動をはじめたころは、主にWeb系の制作会社をみていました。でもふと学生時代を思い返してみると、サークルの仲間と一緒にアプリをつくっていたのがとても楽しかったなと。継続的に改善を重ねながらアプリをつくっていける事業会社に魅力を感じ、そのひとつとして受けていたヤフーに入社を決めました。

現在担当している主な業務内容について教えてください。
入社してからはずっと「PayPayフリマ」を担当しています。フリマアプリとしては後発サービスとなりますが、独自性を意識した機能や施策を積極的に取り入れています。デザインチームではデザイン業務にプラスし、メンバーの興味がある領域に積極的にチャレンジさせてもらえます。私は「サービスとしての軸からブレていないか」「ちゃんと「PayPayフリマ」になっているか」の部分にフォーカスし、一貫した体験づくりに取り組んでいます。ほかにも、新機能の検証やユーザーインタビューを行うメンバーがいたり、新機能の開発にチームとして携わったりすることもあります。
最近は主にリニューアルに向けて整備を進めています。特にサービスカラーが大きく変わることもあり、その新カラーをメインに据えたUIデザインに取り組んでいるところです。
そのなかでも主に私が担っているのは、デザインガイドラインの策定です。もともとはコンポーネントのつくりにばらつきがあり、置き場所もまとまっておらず、「どんなものがあり、どんなデザインがなされているのか」がぱっと見ただけではわからない状態でした。ユーザー体験の観点でも一貫性を欠いてしまいますし、デザイナーにとっても作業しにくい状態になっているなど、デザインガイドラインがしっかり定まっていないことがさまざまな問題のボトルネックになっていたんです。
現在はルールを一本化し、「PayPayフリマ」だけでなく「ヤフオク!」も対象として両サービスに共通したデザインガイドラインをつくっています。私としても、散らかったものを整理するこの業務にはとてもやりがいを感じています。

1日のスケジュール例
- 10:00
- 勤務開始。前日終業後のSlackの確認、返信
- 12:00
- ランチ
- 13:00
- 企画会議
- 14:00
- デザイン相談会
- 15:00
- UI/UXガイドライン定例会議
- 16:00
- 担当案件のデザイン作業、UI/UXガイドライン整備
- 19:00
- 勤務終了
仕事を進めるうえで意識していることはなんですか。
私の仕事は「ここが不便だから、こうなったらいいのにな」という妄想から始まることが多いかもしれません。事例をたくさん探してインプットし、それらを元にしてメリットとデメリットを考慮したりいろいろな人の意見を聞いたりしながら、理想と現実との間の溝を埋め、プロダクトにとって最適な形になるよう模索しています。
業務を進めるなかでは社内のさまざまな人々と関わり合います。自分と相手の意見が異なるケースは多々ありますが、相手の意見がすべて間違っているなんてことは絶対にないと思っています。周りの方々もとても優秀なので、その意見に対しても納得できることがほとんど。そのため、話し合いの際に後ろ盾になるのはやはりクリック率などの客観的なデータで、そういった根拠をしっかり持って判断することを大切にしています。
でも実は、データが示すことと自分が感覚としてとらえているものが大きく乖離するケースはあまり多くありません。「この機能はなくしてもいいかな」と思っていたら、やっぱりデータ上も数値が良くないなど、体感していることがそのまま表れているんです。世間一般のユーザーの目線とたまたま近いのかもしれませんが、自分で自分を客観視している部分もあるのかもしれません。
おもしろいこと・難しいことなど働くうえでこれまでに得た経験を教えてください。
「配送方法 早わかり表」をWebで公開したプロジェクトが印象に残っています。当初は「表にしてWebで公開しよう」とはじめたものですが、やはり表を公開しただけでは見てもわからないのではないかという点が気になっていました。そこで、「ユーザーにやさしいものをつくろう」と企画の方に相談し、企画・デザイナー・エンジニアのプロジェクトチームでディスカッションを重ね、機能を検討していきました。最終的に、現状のような「選択を進めていけば、自分が送りたいものに対して必要な内容がすぐにわかる」という機能を実装することになりました。当初の想定と変わってしまったので少し不安はありましたが、自ら意見をあげたことで良いと思える形にまとまり、結果的にユーザーからも好意的な反応をもらえたので良かったです。

また、入社当初と比べるとプレゼンテーション能力が向上したと感じています。もともと自分自身に対して「意見を持っているわりに、それをうまく人に伝えられない」課題を感じていました。プレゼンテーションに苦手意識があり、良いと思ったものを相手にうまく伝えられなかったんです。
でも上長がさまざまな機会をつくってくれたこともあり、だいぶ改善したのではないかと思います。「説得材料をつくってみたらどうだろう」「ほかのメンバーに意見を聞いてみるといいよ」など、もらったアドバイスを実践してみたり、そこで集まったフィードバックをもとにまた上長と相談したりと、少しずつ経験を積み重ねてきました。なかなかいい資料がつくれなかったり、うまく伝えられなかったりして迷惑をかけてしまったこともありましたが、そういった場を設けてもらい、周囲の協力もあったからこそいまの自分があると感じています。
実際、多くの機会を与えてもらえたことで、自分のやりたいことをやるには当時所属していた開発チームだけでは難しいのかもしれないと気づけました。その経験があったからこそ、「デザインチームにいきたい」と声をあげられましたし、デザインガイドラインを整備するやりがいのある仕事に取り組めているので、こうした機会をもらえたのは本当によかったなと思っています。
入社して良かったと感じることはなんですか。
多くの人が積極的に発信していて、いろいろな意見が出やすいカルチャーがあり、とても魅力的だと感じています。私自身1年目からどんどん意見をあげていましたが、言っても大丈夫な安心感があるんです。風通しの良い社風のため、年次だけで判断して意見を聞いてもらえないこともないですし、意見を言えば話を聞いてもらえるし、検討してもらえます。とにかくフラットで、挑戦させてくれるしそれを評価してくれるので入社してよかったと感じています。
実は入社前に実際に会社に足を運ぶまでは、もっと堅くて上下関係なども厳しい会社なのではないかと先入観を持っていました。でも面接での先輩の話から「意外と柔らかい雰囲気なのかな」と感じるようになり、実際入ってみてもその印象通りの柔らかくて優しい会社だと感じています。
これからのLINEヤフーに期待することや、楽しみなことはなんですか。
具体的な連携事項として今決まっていることはありませんが、LINEのデザイナーはとても優秀なイメージがあり、サービスを磨きつづけているので、そのノウハウに触れられる機会があると思うととても楽しみです。今後お互いの知見を共有する機会などを持てると良いなと思っています。
LINEとヤフーは「ユーザーファースト」の考え方が大きな共通点だと思いますが、デザインガイドラインは各社でルールが異なるはずです。これまでのルールは尊重しつつも、ひとつの会社になることによって良い部分が混ざりあっていくことを期待しています。

今後の目標について教えてください。
今後はWebだけでなくアプリなどもしっかり見ていけるようになって、サービスを総合的に見て最適なUIを考えてまとめあげられる人になりたいですね。デザインガイドラインにしても何にしても質問されたらすぐに返せる「辞書」のような、「加藤に聞けばわかる」と言われるような存在になりたいなと思っています。
直近では「PayPayフリマ」のリニューアルを控えているので、まずはそこに向けていろいろなことを整理し、綺麗なアプリに仕上げていきたいです。今後も「PayPayフリマ」ならではの機能を継続的に出していけるように、デザインガイドラインの整備によって地盤を固め、そういった機能の展開を支える人になっていけるといいなと思っています。
最後メッセージを。
私自身のこれまでの経験を振り返ると、「思い立ったら吉日」で何にでも手を出してやってきたなと思います。成功も失敗もたくさんありましたが、それらを経て自分自身もアップデートを繰り返し、いまにいたっているのだと感じています。ぜひどんどん手を動かして、まずはいろいろなものをつくってみてほしいですね。やってみることが大切ですし、チャレンジして後悔することは絶対にないので、とにかく恐れずに挑戦してみてください。