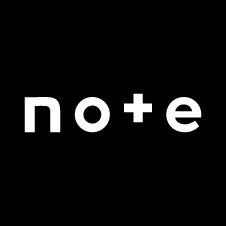福本 博之
LINE NEWSを支える
データアナリスト。膨大なデ
ータで答えなき問いに挑むお
もしろさ
LINE NEWSを支えるデータアナリスト。
膨大なデータで答えなき問いに挑むおもしろさ

福本 博之(ふくもと ひろゆき)2022年入社
マーケティングリサーチ会社のマーケター、データアナリストを経て、2022年12月にLINE(現 LINEヤフー)に中途入社。入社から現在まで、「LINE NEWS」のデータアナリストとして、データ分析に従事。
※本記事は2024年11月に取材したものです。サービス名称や所属は取材当時の内容です。
自己紹介をお願いします。

福本 博之です。2022年12月にLINE(現 LINEヤフー)に中途入社しました。新卒で入ったのはマーケティングリサーチ会社でした。マーケターとして1年間働いた後、データ分析支援を担当する部署への異動を機に、データアナリストとして働き始めました。
前職では、クライアントの有料サブスクリプションメディアの分析支援をしていたのですが、外部協力だったこともあり、分析結果が最終的にどうプロダクトに反映されるかを見届けにくい立場だったんです。また、次々にくる依頼に対応することに追われ、じっくり腰を据えて自分がやりたい分析をしにくい状況でした。次第に事業会社で働いてみたいという気持ちが強くなり、4年近く働いた後、転職を決めました。
入社の決め手は、なんといっても日本でトップクラスのメディアである「LINE NEWS」に関われることでした。もともと大学・大学院で、社会心理学や情報学を学んでおり、メディアコミュニケーションには興味があったんです。
入社以降はずっとデータアナリストとして、「LINE NEWS」を対象としたデータ分析全般に関わっています。現在所属しているチームは兼務も含めて7名で、割と自由な雰囲気で、アナリストの気質にも合っている気がします(笑)基本的には個人作業がメインとなるため、普段はみんな黙々とデータ分析をしていますが、共有やフィードバックなどのコミュニケーションは密に行っています。
現在担当している主な業務内容や具体的な流れについて教えてください。
私のチームで扱っている分析は大きく2つあります。1つは、企画チームからの「この企画を考えたので、こういう数字を出してほしい」というピンポイントな依頼に応えるもの。具体的にはイベント・パラメータ設計、効果測定、定常ダッシュボード作成・運用などで、企画担当者や開発担当者と連携しながら進めます。
もうひとつは、もう少し規模が大きい横断分析です。主にプロダクトの意思決定者が抱えている課題について取り組むもので、1案件あたりのスパンは1~2カ月と長め。「どんなデータを出せば活用してもらえるか」から考えます。私はこちらの領域の担当が多く、現在は業務の約8割を占めています。
過去の例でいうと、「LINE NEWS」の「LINE公式アカウント」で「読まれています」というタイトルの配信を新たに始めたとき、開封率やクリック率を分析しました。きっかけはユーザーボイスにネガティブな声が多かったことが理由でしたが、配信の開封率はそう悪くないことがわかりました。一方で、クリック率に課題があることがわかり、最終的にUIの改善が決まりました。

ほかにも、「LINE NEWS」の「LINE公式アカウント」における生存時間(ユーザーにフォローされてからブロックされるまでの時間)の分析もしていました。配信の開封数を上げるためにさまざまな施策を実施していますが、「ブロック率そのものを下げることができれば、もっと大きな効果が見込めるはず」と思ったことが出発点でした。生存時間分析という手法を用いて、生存時間や生存率にどんな要因がどのくらい関連しているのかを検証しました。
「LINE NEWS」のトラフィックに関する分析も行っています。
たとえば、トークタブ上部にある「スマートチャンネル」という枠の広告比率が上げられる時期がありました。ここには「LINE NEWS」への導線も置かれていたので、トラフィックへの影響が少なからず出ることは元から想定されていました。
しかし、想定以上にトラフィックの減少が大きかったため、トラフィックに関連する複合的な要因を可能な限り分解、抽象化して、スマートチャンネルによる影響がどの程度見込まれるのかを分析しました。
大まかな仕事の流れは、まずは上長との1on1ミーティングなどでプロダクトの課題をインプットしてもらい、それをもとに「どういう数字を出して課題の状況や原因を明らかにし、解決策へつなげるか」の仮説を立てながら検討していきます。実際の分析よりも前段階の準備にかなり時間がかかりますね。
分析は途中でチームメンバーにも共有しながら、内容をブラッシュアップしていきます。「結局何がしたいんだっけ?」「この数字だけだと説得力に欠けるよね」など、率直な意見をもらいながら調整を進め、最終的にチームの合意がとれたものを報告します。ただ、分析チームで「このデータはおもしろいよね」と合意したものが意思決定者にも響くかは別問題。逆に「このデータ、本当に意味あるかな」と半信半疑だったものが、意外に喜ばれることもあります。
1日のスケジュール例
- 8:00
- 勤務開始
- 午前中は基本的に分析作業時間にあてています。
- 13:00
- 上長との1on1ミーティング
- 14:00
- 分析チーム内でのhuddle(進捗共有・相談)
- 15:00
- LINE NEWS全体定例会議
- 16:00
- 分析ディスカッション会
- 18:00
- 勤務終了
仕事を進めるうえで意識していることはなんですか。
「分析の成果がどうプロダクトに活用されるか」を意識しています。とくに私の場合は、事前に与えられた課題に対し、明確なゴールが定まっていないことも多くあります。しかしその分、プロダクトの意思決定者から成果を求められているのは感じます。分析が数カ月の長丁場になることも多いので、「これだけの工数をかけたのに成果がゼロ」というのは自分としても避けたく、「この分析をやる意味は?」「この分析結果は誰が何をするのに役立つのか?」などは常に意識しながら分析を進めています。
それからチーム内の情報共有も心がけています。ひとりで分析していると、どうしても煮詰まってしまうことがありますが、上長やチームメンバーからのフィードバックで道が拓けることもあります。
おもしろいこと・難しいことなど働くうえでこれまでに得た経験を教えてください。

やはりデータの量が多いので、分析しがいがありますね。データ量が少ないと注釈付きの結果になったり、細かい分析軸が設定できなかったりします。しかし、「LINE NEWS」ではそういったことはなく、新しい分析手法にも取り組みやすいです。
一方で難しいのは、プロダクトの意思決定者に分析結果をどう伝え、今後のプロダクト改善に役立ててもらうかです。複雑な分析手法を使うと、そもそも手法を理解してもらうことに時間がかかり、分析結果を説明しても伝わりづらいこともあります。さらに、短く速く、わかりやすいプレゼンテーションも意識する必要があります。1カ月かけた分析を数枚のスライドにまとめ、短い時間でわかりやすく説明するために、どう伝えるか、毎回上長と頭を悩ませています。実際、わかりやすい基本的な分析のほうが「参考になります」と喜ばれることも多いんですよね。それなら簡単な解析手法だけ使えばいいと思われるかもしれませんが、因果関係を検証するのには複雑な分析手法が必要なこともあり、なかなかそうもいきません。こういった試行錯誤は複雑で大変ではありますが、データアナリストとして貴重な経験を積めている感触があります。
入社してよかったと感じることはなんですか。

やはり、意思決定者と直接話せることですね。分析結果を直接説明し、フィードバックをもらい、持ち帰って再度分析して、また提案する…といったプロセスは前職ではできなかったこと。準備は大変ですが、その分やりがいがありますし、裁量も増えました。漠然とした社内の課題に対して、リサーチクエスチョン(調査課題)を立て、ある程度長期スパンで取り組んでいくので、自分のペースで分析を進められています。
仕事以外では、リモートワークを活用して柔軟な働き方ができる点も気に入っています。子どもが小さいので、何かあったときにすぐにかけつけられる安心感は大きいですね。妻の里帰り出産時には、妻の実家からリモート勤務をし、3カ月の育児休暇も取得しました。
今後の目標を教えてください。
現状の課題はプロダクトへの貢献度合いですね。分析結果が活用される割合が半々程度だと、打率としてはまだ低いです。データアナリストとして、「福本に頼めば、有益なデータを出してくれる」と思ってもらえるところを目指したいです。
キャリアに関しては、入社前の面接で、「この先10年くらいはデータアナリストとして現場でやっていきたい」と話しました。面接から約2年経ったいまも、思いは変わっていません。まだまだ現場でスキルを磨いていきたいなと思っています。
やはりデータアナリストは手を動かしてこそだと思うので、あらゆるデータに埋もれられる現場が好きですね。「このデータとこのデータを掛け合わせたらおもしろそう」「この分析軸を加えたら、目新しい結果が出るかも」など、ふとした思いつきをすぐ実行できるのは現場にいるからこそ。思いつきが実を結ぶ確率は1割にも満たないことがほとんどですが、ダメならダメでまた次のことを考えるだけ。そういった試行錯誤のプロセスを楽しいと思える人がデータアナリストに向いていると思います。
これからのLINEヤフーに期待していることを教えてください。
実際のデータ連携はこれからですが、統合作業を乗り越えれば、今後は「Yahoo!ニュース」のデータもシームレスに扱えるようになり、データの量だけでなく、データの種類が増え、分析の幅も広がっていくはずです。「LINE NEWS」と「Yahoo!ニュース」は、コアユーザー層が異なるため、そういった意味でもデータを統合するメリットは大きいと感じます。
「LINE」と「Yahoo! JAPAN」双方のプロダクトの相互送客は今後どんどん加速していくはずです。データアナリストとしても、同じデータを扱えると「ここはYahoo!ニュース側に任せる。ここはLINE NEWS側が強化していこう」など、提案の幅が広がると思います。
最後にメッセージを。
LINEヤフーのデータアナリストは裁量が大きい分、責任もありますがやりがいも大きく、さまざまな経験を積める環境です。
機械学習やAIを活用するデータサイエンティスト寄りの業務をイメージした人もいるかもしれませんが、我々のチームはクロス集計をしてデータをじっと眺めて、プロダクトにどういった貢献ができるかをひたすら考え抜く、泥臭い現場です(笑)。でも、これが楽しいんです。
もちろん社内にはデータサイエンティストが集まる組織もあるため、希望すれば異動もできますし、我々のようなデータアナリストの組織も多くあります。データを扱う幅広い仕事ができる会社なので、データに興味がある人はきっと楽しく働けると思います。興味を持ってくれた方のご応募をお待ちしています。